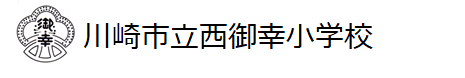10月 みんなの学校生活
10月31日(金)
5年 算数「単位量あたりの量」


どちらが混んでいるか前時の確認 2人で考える


今日は先生と考える子 アドバイスをする先生
単位を揃えてどちらが混んでいるか比べる「単位量あたりの大きさ」の学習、前時で学習したことを確認した後、「どのように人口密度を求めればよいか」を考えていました。人口密度とは、1平方キロメートルあたりの人口のこと。しっかりおさえてから、各自それぞれ「誰と、どこで、どこまで」の計画を立て、学習を進めていました。何を求めればいいのか明確なので、素早く計画を立てて、散らばっていきます。1人でじっくり考えたい子、2人組、3人組になる子たち、「今日は、先生とやろうかな。」と黒板の前に移動する子たち、様々でした。
先生と考える子どもたちも、自力で解けるようになったら自分で考えます。先生は、アドバイスをしながら、教室中を回ります。やる気が出るような声かけが心地よいです。答えが出て、他の子どもたちと共有した後、「今度は、1人あたりの面積で比べてみようかな。」なんて、学習がどんどん広がっていきました。それぞれが問題に真摯に向き合い、できた、わかったと達成感を味わい、どのくらい理解できたか、ふり返りをしていました。
10月30日(木)
4年 道徳「琵琶湖のごみ拾い」


板書を見ながら意見の整理 自分の考えを書く


どんどん考えが広がっていく たけのこ発表続く
4年生の道徳の時間、「琵琶湖のごみ拾い」を読んで、考えを深めていました。ごみ拾いと聞くと、「きたない、よごれる、さわりたくない、めんどう」と素直な意見が出されました。しかし、学習を進めていくと、「ああ、気持ちがいいなあ。」「ごみがなくなってきれいになった。」「まわりの人も気持ちよくなる。」「うれしい。」「人は誰かの役に立ちたい。と心の奥で思っている。」など、深く考えていました。よく考えることで、その人の道徳的価値が育っていきます。
深く考えて、意見をまとめた人たちは、清々しい表情で、「たけのこ発表」(早く立った人が自主的に発表する)で、わかったことを自信を持って、発表していました。
10月29日(水)
2年 国語「運動会の思い出をのこそう」


心に残った瞬間がよくわかるように日記に書く


自分が頑張ったこと みんなで頑張ったこと
各学年ごとに、運動会のふり返りをしています。全力を尽くした頑張りや気持ちを交流したり、GIGA端末に入力したり、作文に書いたり、絵日記にしたりして、心に残そうとしています。
2年生は、絵日記にして、ふり返っていました。ダンスのこと、玉入れのこと、全力走のことを書いている子が意外と多いようでした。「全力走は、4位だったけど、自分としては一番頑張ったし、楽しかったんだ。」、「ぼくも3位だったけど、すごく頑張ったんだ。」、「ぼくは、玉入れ。練習の時はいつも赤組が勝っていたのに、本番は白が勝ってびっくりしたんだ。」、書いている途中で、気持ちを教えてくれました。全力走の順位がよくなくても、来年は、もっと頑張るという気持ちを持っていました。きっと、お家の方々の声かけやアドバイスが効いていたのかも知れません。前向きに捉え、次はもっと頑張るぞとの意気込みが伝わってきました。
10月28日(火)
令和7年度 「運動会」 全力で向かった運動会


ダンシング玉入れ にしみソーラン2025


たのしくおどろう 引いて走って綱引き超決戦


応援団が競技を盛り上げ 赤白、引かず応援合戦


感動!踏み出し、飛躍! 繋げ、にしみの思い!


肩を組んで校歌の合唱! 応援団長インタビュー
待ちに待った(25日から28日に延期)運動会が、青空のもと、開催されました。5・6年生が、「28日の運動会、頑張ろう!」と声をかけてくれたおかげで、全校児童は、モチベーションを落とさずに、朝から笑顔で、しっかり並べ、全力で取り組みました。
一つひとつの演技や競技、応援に、「最後まであきらめず、頑張ろう!」という想いが感じられ、感動の連続でした。保護者の皆様や地域の皆様の応援、声援をいただき、子どもたち自身、達成感に満ちた運動会となりました。ありがとうございました。
この日は、3年生から6年生は、6時間授業でした。5・6年生は、6時間目に体育館に集まり、運動会とふり返りと、6年生から5年生に繋ぐ言葉を送っていました。耳を傾けると、「悔いが無いほど、全力を出し切りました。」「5・6年の連携がすごいと思いました。明日から、もうフラッグができないと思うと残念です。」など、頑張ってきた運動会練習や学年を超えて繋いだ絆をそれぞれが感じていることがわかりました。今日で終わりではありません。全力でやり遂げる力と相手を思いやる力の清々しさを忘れずに、この経験を明日からの学校生活に生かしていきましょう。
10月25日(土)
運動会は28日(火)に延期 午前中授業


切り替え上手な2年 3年は、理科「重さ」


5年テスト直しと分析 6年国語「柿山伏」


5年 家庭科の授業も 5年国語「詩の鑑賞」
運動会が延期になった日の午前中授業は、子どもたちのモチベーションもさがります。しかし、西みの子どもたちは、気持ちを切り替え、今日やることをしっかり学習していました。
5・6年 ロードを作って、運動会 頑張ろう!


ピロティでロードを作り、運動会、頑張ろうね!
帰りの時間には、5・6年が、自主的にロードを作り、下学年に「28日火曜日の運動会、がんばろうね!」と、声をかけていました。ロードを通る子どもたちは、5・6年生の熱量に驚いていましたが、「うん。私も頑張る!」「運動会、楽しみだよ!」と言って、笑顔で帰っていきました。このロードも伝統になりつつあります。お楽しみは、先に延びましたが、晴天のもと、のびのびと競技や演技をしましょう。また、PTAより、「頑張ったで賞」のジュースをいただき、本日持って帰りました。お家で冷やして飲んで、当日、力を発揮しましょう。なお、運動会が延期になり、28日(火)に、お子さんの頑張る姿を見られない保護者の方もいらっしゃると思います。申し訳ございません。ご近所やお友達に声をかけ、動画をお願いするなどして、ご対応していただけるとありがたいです。それでは、28日(火)の運動会が、盛大に執り行われますようにと願っております。「西み、ファイト!!!」
10月24日(金)
真剣に取り組んだ運動会練習 前日準備


各学年の準備をする用具係 勝敗の仕方を結審係


明日の成功をみんなで祈り、仲間と円陣を組む


最後は、ハイタッチ! 全力で臨む5・6年生!
運動会の前日準備、5・6年生が集まり、それぞれの係ごとに、最後の確認をしました。降ったりやんだりする雨空のもと、明日の晴れを祈り、全力で準備に取り組む5・6年生。自ら率先して動く姿は、素晴らしかったです。終わりは、誰からともなく円陣になり、仲間を待っていました。すっかり西みの伝統となった「円陣」、この日この時のために、声をかけ合い丸くなっていました。5・6年生のみんなと先生方が一つになり、雨を吹き飛ばし、みんなが創り上げた運動会を成功させようと、肩を組み、声をだしました。きっと、明日は、全力で競技や演技を披露してくれるでしょう。保護者の皆様も応援、声援をよろしくお願いいたします。
10月23日(木)
4年 算数「一つの式に表して答えよう」


あめの値段は20✕3 180円で何袋買える


何算?わり算じゃない 180÷(20✕3)だ
4年生のクラスから、「えー、違う!」「そうそう!」と楽しそうな声が聞こえてくるので、授業参観に行きました。算数は、どのような考え方をしてもよいのです。二つの式で答えを出す子、一つの式で答えを出す子がいてよいのですが、一つの式にした方が答えを出すのに簡単な場合があります。なので、一つの式にして答えましょうという問題が随所に出てきます。それは、子どもたちには意外と難しく、理解困難な場合があります。4年生では、一斉指導で、一つずつ問題を読み解きながら、二つの式を一つにする授業をしていました。
問題「1こ20円のあめが1ふくろに3こ入って売られてい、あす。180円で何ふくろ買えるでしょうか」、場面を想像して、みんなで解いていきます。「1ふくろの値段は、20✕3で求められます。」「180円持っていて1ふくろは60円だから、180÷60になります。」すぐに求められる子、友達の考えを確認している子、自分なりに考えている子と、様々でしたが、最後は全員がすっきりした表情になっていました。みんなで、一つずつ考えていくことも大事なことです。
10月22日(水)
運動会へ向けて 盛り上がりを見せています


スポーツ委員会の応援 ソーランのはっぴに感激


赤、黄色、白、青、選抜リレー選手の意気込み!
25日(土)の運動会に向けて、どの学年でも、盛り上がりを見せています。少ない時間の中、各学年の競技や演技の練習に、休み時間は、選抜リレーや応援団の練習、声援が飛び交っています。また、気温が低い日が続いているので、かぜをひかないように、インフルエンザにかからないように、子どもたちは体調管理をしています。全て、自主的な行動を先生方が支えています。自分たちがどうするか決めているので、一人ひとりの行動が素敵なのです。
スポーツ委員会は、みんなに元気を出してもらうために、昇降口に大型テレビを出して、応援動画を流しています。3年生は、今日の帰りに、「ソーラン」で着るはっぴとはちまきを受取り、本番が待ち遠しくなったそうです。代々大切に受け継がれているはっぴです。「◯番を着て、かっこよく踊るんだ!」と意気込みを語っていました。
ピロティから見えるのは、選抜リレーの各チームの紹介ポスターです。赤「レッド ウォーリアーズ」、黄色「イエロー チーターズ」、白「ホワイト ニンジャーズ」、青「ブルー シャークズ」と、仲間で名前を決めました。意気込みも書いてあります。自分たちで一秒でも速くするためにどうしたらよいか考えているので、バトンパスが上手になりました。当日を楽しみにしていてください。
10月21日(火)
5年 理科「地面を流れる水」


流れる水には、どんな働きがあるのか。説明を。


根拠を持ってみんなが納得できるように話します
5年生は、理科の時間。4年生の時には、地面に降った雨水は、高い所から低い所に流れることを学びました。5年生では、「流れる水には、どんな働きあるのか」について、考えます。この時間には、上流、中流、下流の石をそれぞれ選んで、どうしてその場所の石なのかをみんなに説明する授業でした。3択なので、答えは、なんとなくわかります。ここでは、知識だけでなく、周りの人の意見を聞いて、自分の意見を発表できることを学習しているようでした。
グループで話し合った後、みんなの前で意見を発表する人を決めます。決め方は、ジャンケン。誰でも、発表できるようにするためにクラスで積み重ねてきたようです。順番に、画面を操作して、なぜ、ここの石はこれだと思うのかを発表していきます。前の人の発表を聞いて、違った表現をして、聞いている人たちを納得させているのは、発表の仕方が育っているなと感心しました。
10月20日(月)
全校練習 開会式・閉会式の練習


体育館の練習となったが、応援の声がこだまする
先生の話を聞いて、きびきびと動く子どもたち。最初で最後の練習が体育館になりましたが、賢い西みの子どもたちは、25日にも、しっかり動くことでしょう。当日の閉会式の最後には、運営委員会によるお楽しみのイベントがあります。1年生のキョトンとした顔がかわいかったです。
自校献立の日


ジャンボ餃子と味噌ラーメン 嬉しい!食べるぞ


おいしい顔って、こんな顔! 献立に大喜び!
年に2回の自校献立の日。今回は、「ジャンボ餃子、味噌ラーメン、ご飯半分、焼きのり、ジョワ」でした。毎日、給食を楽しみにしている子どもたちですが、今日はまた特別。朝や休み時間、給食室のガラス窓越しに、給食ができる様子を見ていました。「大きな餃子だね。」「ジャンボ餃子って、あんなに具を包むんだ。」待ち遠しそうに眺めています。
そんな3年生の教室へ、給食の時間に行ってみました。「今日の自校献立はいかがですか?」「最高!」「おいしい!」とニコニコ笑顔で答えてくれます。あまりにも、おいしそうに食べているので、素敵な笑顔をパチリと写真に写しました。「おいしい顔って、どんな顔?」「こんな顔!」と、みんなの「おいしい顔」でした。運動会前に、スタミナをつけるようにと、考えられた献立でした。
10月17日(金)
全校児童 運動会の応援合戦の練習


朝一番は応援合戦の練習 相手のチームにエール


応援の練習はバッチリ 5・6年生のフラッグも
今年の運動会は、練習時間を縮めて効率よく練習しようと、先生方も児童たちも、工夫し、集中して練習をしています。今日は、初めての応援合戦の練習でした。
だんだん声も大きくなり、懸命に応援をする子どもたちです。人気がある応援団を中心に、力いっぱい応援合戦の練習をしました。担当の先生から、「上手、バッチリです。」と褒められ、みんなにっこり。当日も、熱の入った応援合戦が見られることでしょう。楽しみにしていてください。
時間が変わり、みんなの運動会を創ってくれている5・6年生のフラッグの演技が始まりました。位置を確かめ、フラッグを操る姿に頼もしさを感じました。これまた楽しみですね。
10月16日(木)
2年 人生初の6時間目


人生はつの6時間目 1組は、算数のテスト


2組は、図書の時間 本の世界に浸っているよう
2年生の教室に行くと、黒板に、「人生はつの6時間目」と書かれていました。そうです、2年生は、今日から6時間授業が始まるのです。6時間目が始まる前に、感想を聞いてみました。「えー。疲れちゃう。」「6時間目までもつかな。」から、「少し不安だけど、楽しみ。」まで、いろいろ話してくれました。
6時間目は、1組は算数のテスト、真剣に問題に取り組んでいました。2組は、図書の時間です。借りている本を返した後は、お友達と読みたい本を探して、その後は、静かに静かに、選んだ本を読んでいました。6時間授業が加わった2年生。だんだんに慣れて、また一つお兄さんお姉さんになっていくのでしょう。
10月15日(水)
後期始業式


後期の目標を発表 目と耳と心でしっかり聞く


新しい始まり校歌の合唱 児童会テーマの前で
後期始業式、今日から3月に向かって新たなスタート。4日間のお休みに出かけた人たちも多かったため、体育館に全校児童が集まった時は、どんよりとお疲れムードが漂っていました。しかし、始業式が始まると、みんなシャッキっとして、お話をしっかり聞いていました。後期の目標を決めてくるように伝えていましたが、まずは、目の前の運動会の目標になるのでしょうか。西みのみんなは、前向きに毎日を過ごしています。
今年の児童会テーマの作成が終わり、「昇降口に貼ったので見に来てください。」と教えに来てくれました。「素敵!細かい部分までこだわっているね。」と言うと、「自信作です!」と嬉しそうに説明してくれました。児童会テーマ『みんなで手をとり輝こう ~未来へつなげる西ファミリー~』太陽のように輝き燃えて、未来へと繋いで行ってほしいです。
10月10日(金)
前期終業式


頑張ってきたことを発表 みんなが声が一つに!


よい姿勢でお話を聞く陶芸コンクール受賞者たち
前期終業式、体育館に全校児童が集まりました。子どもたちの顔を見ながら話ができるのはいいなぁと思いました。西みのよい子は、しっかり話が聞けました。これから、10月25日の運動会に向けて、整列したり話を聞いたりしていきます。このような場所でも練習になります。
昨年から「のびゆくすがた」の所見は、後期にまとめて書くようになったので、「自分は何を頑張ったのか、どうやって頑張ってきたのか、何ができるようになったか、何がわかったのか、説明してください。」と話しました。お子さんからの説明に耳を傾けて、よく聞いてください。そして、アドバイスをしていただけると励みになります。一人ひとり、頑張ってきました。終わりに、9月の歌「ビリーブ」を歌いました。子どもたちが大好きな歌です。柔らかく優しい声で歌い、響き合った歌声が体育館に響いていました。
もう一つ、全国陶芸かさまコンクールで受賞した人たちの表彰がありました。なんと18名が前に出て、大きな拍手をもらいました。西みの子どもたちの陶芸の力は素晴らしいです。今年も素敵な作品ができあがっています。
10月9日(木)
1年 生活科「アサガオのつるでリース作り」


支柱からつるを取っていく2人組で丸めて止めて


協力すると簡単だね!たくさんのリースができた
今日の1年生は、4月から育てて、いっぱい観察して、いっぱい楽しませてもらったアサガオに感謝を込めて、最後にリース作りをしました。支柱に絡まっているつるを取るのは大変でしたが、上手に取っていました。長いつるを丸くするもの2人組になって、くるくる丸めて1人が持ち、もう1人がモールで止めてできあがり!上手にリースを作っていきます。4月から、協力することを学んできた子どもたちです。あっという間に、たくさんのリースができあがりました。乾かして、図工の時間に飾りをつけて、思い思いの自分のクリスマスリースを作ります。できあがりが楽しみです。
10月8日(水)
1年 生活科「むしとなかよし」


虫を育てるには何で調べる 本や図鑑で調べるよ


暗い所が好きなんだ 壁にずらりと並んだ秘密


虫の秘密を発表します 本当だ!おしりが大きい


ほらね。ジャンプしたね 動いたよ。かわいいね。
1年生は、ヤゴを育てて、10匹以上トンボにかえした経験に自信を持っています。そして、虫の声が聞こえるこの頃、学校の校庭にいる虫を探して、育てる計画を立てています。虫取り網と虫かごを用意して、校庭に行きました。5分もたたずに「虫がいない。」「虫が見つからない。」と諦めムードになりました。それが、今では、休み時間中、虫探しに夢中になっています。虫がどこにいるのかも見当がつくようになりました。
今日の5時間目の学習は、2組は、探した虫の住みやすいすみかを作るため、本や図鑑を使って調べました。どんどん見つけて、グループの人たちと協力して調べていました。1組は、虫を観察して「虫のひみつ」を発表していました。壁にも、今まで観察して見つけた秘密がびっしり貼られていました。お友達の秘密を聞いた後、本当かもう一度確かめに観察をしていました。
どちらも昆虫博士のように、自信満々に学習していました。虫が好きな子はもっと好きになり、虫が苦手だった子は虫を怖がることがなくなりました。調べて、飼って、観察して、じっくり関わり、虫とすっかり仲よくなった子どもたちでした。さて、これからは虫たちをどうするのかな。
10月7日(火)
休み時間


リレーの練習が始まった 大勢の子が校庭へ


大きいバッタを捕まえた 音楽が鳴ると昇降口へ
だんだん秋らしくなり、今日は涼しく、外で遊ぶには絶好な日和です。校庭では、運動会の赤白リレーの練習が始まっています。しかし、休み時間は、練習の合間をぬって、たくさんの子が校庭に出て、遊んでいます。邪魔にならないように、危なくないようにと、絶妙なタイミングで散らばります。サッカー、ドッジボール、バスケットボール、一輪車など。トラックを使って練習が始まるとトラックの外で遊んでいます。遊具がある方では、ブランコ、ジャングルジム、そして、虫探し。1年生は、虫とり網と虫かごを持って、虫探しに夢中です。バッタやコオロギなど秋の虫も、コロッコロと丸く大きくなってきました。1年生も虫を捕まえるのが上手になってきました。過ごしやすい日が続くとよいですね。
10月6日(月)
2年 生活科 「いもほり)


野菜名人林さんのレクチャー 早速、つるを引く


土の中にはさつまいもが こんな大きなおいも!


「取ったどー!」喜び つるは、干してリースに
2年生が植えたさつまいもが大きくなっていると聞いて、今日はいもほりをしました。軍手をはめて、赤白帽子をきりりとかぶって、「早く、大きなさつまいもを取りたいよ。」と意気込み、畑に向かいました。野菜作り名人の林さんのレクチャーを聞き、早速、いもほりに夢中になりました。「つるを伝って行くとさつまいもがついているよ。」「つるが切れても土の中にさつまいもがあるから、シャベルや手で、よく探すんだ。」声をかけ合い、力を合わせて、いもを掘り出していきます。
大きなさつまいもが取れて、大喜び!小さなさつもいもを見つけては、「かわいい!」とご満悦!さつまいもは、豊作。どんなさつまいも料理を作ろうかな。つるは、干してリースにするそうです。先輩たちから受け継いだ畑も3年目。土もよい土になりました。次は、何を植えようかな?いろいろ考えを巡らす2年生です。
10月3日(金)
4年 総合「小向の獅子舞を知ってもらいたい」


保存会の方も駆けつけて 保護者の方々の参加も


ビンゴで獅子舞を教えるくじ引きで獅子舞グッズ


くじ引きで獅子舞を教える 獅子舞クイズに挑戦
4年生は、社会科で、古くから地域に伝わるものとして「平塚の七夕」について学習した後、自分たちの住む小向にも、300年も伝承されている「獅子舞」があることに気づき、総合的学習の時間で調べてきました。
アンケートをとってみると、「小向の獅子舞」は、意外と知られていないことがわかり、是非、知ってもらいたい、見に行ってもらいたいとの思いから、「獅子舞イベント」を開催しました。休み時間に体育館でやりますと宣伝していたので、全校児童や保護者、獅子舞保存会の方々も、来てくださいました。「どうしたら、みんなが興味をもって獅子舞のことをわかってもらえるか。」について、よく考えました。「クイズに答えてもらって知ってもらう。」、「みんなが好きなビンゴをやりながら知ってもらう。」、「くじ引きを引いて、獅子舞のことを知ってもらって、賞品もあげたら喜ぶ。」、「射的もいいんじゃない。」、まず、みんなが興味をもってくれるブース作りにして、獅子舞に関することを知ってもらえるようにしていました。よく工夫されていて、獅子舞のことがわかり、もらって嬉しい景品もついてきました。
さて、明日、明後日は、小向八幡神社例大祭です。10月4日(土)は、午後6時30分から小向会館にて、10月5日(日)は、午前10時から八幡神社にて、「小向の獅子舞」が舞われます。是非、お子さんと一緒に、獅子舞を見に行ってください。
10月2日(木)
5年 図工 木版画「あの時の一瞬」


彫り方を工夫している人たちの説明 彫りに集中


集中しながらも、時々おしゃべりでリラックス
前日に、5・6年生の版画を羨ましがっていた4年生。今日は、5年生の彫りです。5年生は、余裕があります。白黒計画を立て、後は彫るのみ、同じ三角刀でも、力加減によって、線が細くも太くもなるので、調整しています。縦線、横線によっても、表し方が変わってきます。迷った時は、周りの友達や先生に相談して、決めています。時々、おしゃべりをしながらリラックスしているので、図工の時間が好きと言う人たちが多くいます。6時間、緊張が続くと疲れてしまいますね。
5年生の版画を見ていると、何をしているのかわかります。それを主題と言うのですが、はっきりわかるのが、よい作品です。つい先日行ってきた八ヶ岳自然教室で食べたルバーブソフトクリームを友だちとおいしそうに頬張っている作品もありました。誕生日のケーキに喜んでいる自分、お父さんとお買い物に行って楽しい自分、ジェットコースターに乗っている自分、・・・。みんな最高の一瞬を彫り進めていました。4年生が羨ましくなるのも、頷けます。
10月1日(水)
4年 図工「初めての彫刻刀」


真剣に先生の説明を聞く おっかなびっくり!


刃先に手を置かないを守る 慣れてくると余裕!
4年生は、初めて木版画に取り組みます。真新しい彫刻刀が光っています。安全に取り組む注意を確認して、三角刀、丸刀、切り出し刀の使い方を先生のデモンストレーションで確認しました。
まずは、小さな木版を使って彫刻刀の試し彫りです。最初は、「ドキドキする。」「先生みたくうまくいかない。」「上手く彫れない。」と言っていましたが、掘り進めていくうちに、「何だか上手くいった!」「おもしろい!」という声が聞かれ、彫り終わる頃には、「5・6年生みたいな作品を作ってみたい。」と意欲を見せていました。用意していただいた彫刻刀、大事に使っていってほしいです。