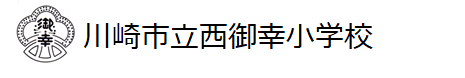6月 みんなの学校生活
6月30日(月)
5年 総合「このまちに住んでよかった!すてき人カードをつくろう」


すてき人カードを作るために どの魅力を伝える


魅力「好きだ」「まちのため」「その人にしかない」


何がその人の魅力か 出揃ったシートを見比べて
今年度の校内研究のテーマは、「西ファミ大好き!このまち大好き!ひと・もの・こととつながる授業づくり~学校や地域の教材化と資料の作成を通して~」です。来年度70周年を迎える西御幸小学校です。もっともっと学校が大好きになってほしい、もっともっと自分たちが住むまちを大好きになってほしいとの思いをもち、学校や地域の教材化と資料づくりを通しながら、実現していこうと研究を進めています。今日は、5年生の校内研究授業日でした。5年生は、このまちに住む「すてき人」を探し出し、インタビューを繰り返してきました。たくさんの情報から、その人たちの魅力を引き出した紹介カードを作って学校のみんなに伝えようと張り切っています。
1組は、情報を整理し、「どの魅力を伝えたらいいか、順位を決めよう」の課題で、情報をプラミッドシートに貼りながら整理・分析をしていました。魅力を1,好きだ!(性格・人柄)、2,まちのため(活動・まちへの思い)、3,その人にしかない(自慢・尊敬)、3つの視点をもち、インタビューカードを見返したり、グループで話し合いを重ね、付箋に書かれた情報の順番を何度も貼り直していました。そして、その人はどのような人かまとめていました。
2組は、次時の「友だちと意見を出し合って、カードに書く魅力を決めよう」の課題で、ピラミッドシートをもとに、説明する人だけが残り、他の人たちは、各グループを回って自分の意見を言って周っていました。他の人の意見を聞いて魅力を伝える順番を変える場面、でも、と、こだわって順番を変えない場面が見られ、どの子も主体的に考えていることがわかりました。「他の人の意見を聞いて、気が付かないことに気付いたり、新しいことに気付かされて、意見交換してよかった。」と、感想を言っている子がいました。これからの変化が激しい時代には、「考えて、調べて、自分の意見がもてる人」が必要になっていきます。じっくりと考えをもつ時間となりました。
6月27日(金)
1年 生活科「梅ジュース作り」


うめジュースパワーについて 落とさないように


梅、氷砂糖、梅、氷砂糖、梅、氷砂糖の順番だよ
今日は、冷凍庫で凍らせた梅と氷砂糖で「梅ジュース」を作ります。飲んだことがない子は、「私、梅が嫌いなの。ジュースも飲めないかも。」と訴えてきました。「梅が苦手なのは、梅干しですっぱいからでしょう。」「ジュースができたら、なめてみて、おいしかったら飲んで、だめだったら飲まなくてもいいよ。」と言うと、ほっとしていました。飲んだことがある子は、「甘くておいしいよ。」と教えてくれました。
栄養教諭の先生が、「うめジュースパワー」のお話をしてくれました。「うめ・・・びょうきからまもる、さとう・・・からだをうごかすエネルギーになる、(前に栄養の授業をしたけれど覚えているかな)うめとさとうをたすと、あつさにまけないからだになるんだ。」「すごいパワーがあるんだね!」
二手に分かれて、梅を一段、その上に氷砂糖を一段、その上に梅、その上に氷砂糖を重ねていきました。1人梅を1個、氷砂糖を1つずつ、何回も何回も繰り返しました。段々と上手になり、慣れてきました。そして、いつの間にか、「おいしくなぁれ、おいしくなぁれ、おいしくなぁれ!」の大合唱となりました。
2週間くらいで、できあがります。おいしい梅ジュースになるとよいですね。
6月26日(木)
1・2年「おはなし会」


物語に引き込まれる子どもたち 本の読み聞かせ


今日のお話はこの本からと紹介 雰囲気も大事
今日は、おはなし会です。ストーリーテリングの皆さんが来校されて、1・2年生は、お話の世界に引き込まれました。本の読み聞かせもよいけれど、「語り聞かせ」も、またよいものです。お話を聞く子どもたちの目や表情を見ながら、気持ちに合わせてお話をします。子どもたちは、「お話を覚えているなんて、すごいよ。」と驚きます。お話をしている方をじっと見て話を聞き入る子、つぶやきながらお話を聞く子と、それぞれですが、しっかりとお話を楽しんでいました。
おはなし会プログラム、1年生は、 1.ふしぎなたいこ、2.おいしいおかゆ、3.えほん、4.おおかみと七ひきの子やぎ、です。2年生は、1.大工と鬼六(日本の昔話)、2.ついでにペロリ(デンマークの昔話)、3.絵本、4.マメ子と魔もの(イランの昔話)、です。どこが気に入ったか、みんなそれぞれ違ってよいのです。お家での話題となるように、プログラムを載せました。
最後に、「ろうそく ふっ も一つ ふっ これでおしまい おはなし会 楽しい楽しい おはなし会 ♫」歌で静かに終わりました。
6月25日(水)
5年 体育「アメリカンフットボール体験」


パスボールをキャッチ ディフェンスをかわす


回転をつけてパス 1人タックルの後は4人で


盛り上がるインタビュー 「フロンティアーズ!」
アメリカンフットボールで活躍している「富士通フロンティアーズ」の選手7名の方々が、5年生の体験学習にいらしてくださいました。5年生は、選手の皆さんの鍛え抜かれた体にびっくり!圧倒されていました。1、大きいパスをキャッチする場、2、楕円形のボールを投げる場、3、タックルの場、4、ボールを持ってディフェンスをかわす場の4つのブースに分かれて、ローテーションで、アメリカンフットボールに挑戦しました。楕円形のボールを扱うのは、とても難しいのですが、上手くボールをキャッチできたり、上手くパスできたり、上手く肩からタックルできたり、上手くディフェンスをかわせたりできると、思わず笑顔で「ヤッター!」と喜んでいました。あっという間の1時間でした。
練習の後、質問コーナーがありました。選手の皆さんに聞いてみたいことがたくさんあるようで、次から次に手があがりました。「アメリカンフットボールを始めたきっかけは、何ですか?」から、「選手の皆さんにとって、アメリカンフットボールとは、何ですか?」まで、意外と深い内容の質問が多くありました。総合で行っているインタビューの成果が出ていました。選手の皆さんも一人ひとり思いを語ってくださいました。中でも、アメリカンフットボールは、走るのが早い、走るのが苦手でもパスが上手、守りが得意など、100人いたら100人の活躍の場があるスポーツだそうです。それから、選手の皆さんも、子どもの頃は、違うスポーツをやっていたけれど、かっこよいと思ったり、チームプレーにあこがれて、アメリカンフットボールを始めたというお話が心に残っています。
最後は、記念撮影です。「コ゚ーゴー。」「フロンティアーズ!」の応援のかけ声で決めました。本物にふれることは、子どもたちの興味・関心の心を揺さぶり、学ぶ意欲につながります。当日、TVKテレビの取材も入り、ニュースの時間に放送がありました。
6月24日(火)
2年 国語「えんそくの思い出を書こう」


楽しかったことを思い出そう 文章にしよう


思ったことも書こう 最後に絵を書こう
2年生の教室に行くと、昨日の遠足の日記を書いていました。「いつ、どこで、だれと、何をした、思ったこと」を落とさず、「見たこと、見つけたもの、言ったこと、聞いたこと、思ったこと」を書くよ。黒板の板書を見ながら、動物園の地図、テレビの画面を見て、忘れた動物は、GIGA端末で調べて、資料がたくさんあるので、楽しかったことや嬉しかったことは、すぐに思い出せました。みんな集中して書いています。「レッサーパンダの鳴き声を聞いた?」と聞くと、「聞いていないんだけど、YouTubeで聞けるよ。」と調べ方を教えてくれました。2年生ともなると、何でもできるんだと感心してしまいました。
ペンギンやレッサーパンダ、ホッキョクグマの赤ちゃんとお母さんを書いていました。楽しい思い出がいっぱいあったようで、いつもより、詳しくたくさん書いていました。1年生と仲よくしたことを書いている子もいました。書く材料がたくさんあると、スラスラかけるのですね。絵も丁寧に書いていました。学校に来られた時に、読んであげてくださいね。
6月23日(月)
1・2年 遠足「ズーラシアに行ってきました」


記念写真みんないい表情 グループごとに出発!


オカピとハイポーズ! おいしいお弁当パクパク


コロコロ広場でコロコロ 自然がいっぱい楽しい
1・2年生は、遠足で「ズーラシア」に行ってきました。各クラスごとに記念写真を撮って嬉しそう!それから、グループに分かれて、動物めぐりの旅に出かけます。ぴかぴか班ごとに分かれての探検になりますが、仲よくなろう会に、楽しく遊ぼう会を行っているので、グループの協力は万全です。仲よく、相手を思いやって、動物をしっかり見ることができました。この日は、ホッキョクグマの赤ちゃんが公開されていたので、並んででも見ようとするグループと他の動物をじっくり見ようとするグループに分かれていました。ホッキョクグマの赤ちゃんが見られたグループはラッキーでした。時計係さんが時間を見てくれたので、全グループ程よい時間で回ることができました。
かなり歩き、走ったので、お腹もペコペコ、全員が日陰に入る大きな木の下で、おいしいお弁当をいただきました。「見て見て!」とお家の方が作ってくださったお弁当を誇らしげに見せてくれました。そして、パクパクと全部たいらげていました。おいしいお弁当を用意してくださって、ありがとうございました。食べ終わった後は、自然がいっぱいのコロコロ広場で、いっぱい遊びました。芝生の坂があるコロコロ広場でコロコロと回る子どもがたくさんいました。お洗濯が大変かもと思いましたが、そんなことができることはそうそうないので黙認してしまいました。「昨日は、楽しみで夜中に何度も起きちゃった!」と言う子もたくさんいました。みんなが楽しく過ごせて最高の遠足でした。お話を聞いてあげてくださいね。
写真屋さんも同行してくださったので、とってもよい写真がたくさん撮れたようです。後日、販売しますので楽しみにしていてください。
6月20日(金)
全校 「にしみ Happy タイム」

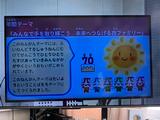
にしみ♫ にしみ♪ 児童会年間テーマ決定!


ランチ委員会による読み聞かせ「いただきます」
朝会のない火曜日の朝は、子どもたちによる校内放送「にしみHappyタイム」の放送があります。今週の火曜日は、プール開きがあったため、イレギュラーに金曜日の朝になりました。今朝の放送は、運営委員会より、「児童会年間テーマ」の発表と、ランチ委員会による、本「いただきます」の読み聞かせでした。
年間テーマ「みんなで手をとり輝こう 未来へつなげる西ファミリー」に決定!と発表がありました。 この年間テーマは、来年度70周年を迎える西御幸小学校の全校児童が一人ひとり助け合いながら、みんなで輝いていこうという思いが込められています。このテーマは、太陽のように輝いていきたいという言葉をモチーフに代表委員会で決まりました。一人ひとりが輝いているにしみの子どもたちです。未来に向かって太陽のように、温かく、時には熱く、輝き続けてほしいです。素敵なテーマが決まりました。
続いて、ランチ委員会より、本の読み聞かせがありました。みんながおいしく食べている食事は、材料となっている動物や植物も、それらを育てている生産者さんたちも、それらを調理してくださる人々も、毎日、ものすごく一生懸命なのです。あなたの体を作っている栄養です。だから、「いただきます」と言って、感謝しておいしく食べましょうという内容のお話でした。とってもよいお話でした。ランチ委員会の皆さんは、毎日お昼の校内放送で、今日の給食についての紹介をしています。また、栄養黒板に、今日はどのような食材が使われていて、どのような栄養となるか、目に見えるように掲示を続けています。
6月19日(木)
1年 生活科「がっこうたんけん」


社長になる椅子に座って この部屋は事務室


ピロティを支えている柱 用務員さんと仲よしに
1年生の学校探検も3回目になり、「1年◯組の〇〇です。学校探検に来ました。入ってもいいですか。」と、特別室の入室の仕方を覚えて、元気な声で入って来ます。学校の様々な場所に出かけ、中に入って教室にはないその部屋にあるものを探して、絵を書いていきます。1年生が作っている学校の地図もできあがりに近づき、学校のどこにどんな部屋があるかわかってきました。
校長室を訪れた子どもたちは、お客さんがたくさん来るので、たくさんのハンガーを書いたり、校長先生やPTA会長さんがずらりと並ぶ写真を書いたりしていました。「なぜ、大きなテーブルとたくさんの椅子があるのでしょう?」と聞くと、「会議をするからです!」と答えていました。ふわふわな椅子に座って「社長になれる椅子だね。」と言って喜んでいました。「大きくなったら、是非社長になってほしいな。」と言うと「はーい!」と答えてくれました。
「このお部屋は何?」「事務室だよ。ここに書いてあるよ。」と指さして教えてくれました。たくさんケースがあり、開けるとみんなが使う文房具が種類別に入っているのを見て、「お店屋さんみたい。」と、目を丸くしていました。大切に使ってくださいね。
ピロティを見に来た子たちは、青・緑・黄色の太い柱を書いていました。「太い柱で天井を支えているんだよ。」と教えてくれました。壁画を指さして、「こっちの絵は、太陽があるから朝で、あっちは、月があるから夜なんだ。」本当によく見ているものです。
用務員室では、用務員さんが使う道具がたくさんありました。「これは、蚊取り線香だ。何に使うのかな?」と聞くと、「草刈りをする時に蚊に刺されないようにつけているんだって。」おもしろいものに目がいくと感心しました。
学校にいる人たちと関わって、仲よしになってほしいです。学校にあるものを見つけて、学校が大好きな子になってほしいです。
6月18日(水)
6年 租税教室


税金についてのお話 真剣に聞き入る6年生


税金クイズ 誰が残るかな 1億円は結構重い
川崎南法人会の方々が来校され、6年生は、税金について学習しました。「税金とはどのようなものなのか」「税金は何に遣われているのか」について、わかりやすくレクチャーしていただきました。
世界の消費税は、日本10%、韓国10%、イギリス20%、イタリア22%、スウェーデン25%と、国によって税率は違います。福祉国家と言われるスウェーデンは、医療費無料、高校無償化など、福祉を充実させるために財源である税金を高くする必要があります。日本では、国に納める税金と地方に納める税金があります。例えば、学校を作るには、お金が必要です。校舎10億円、体育館2億円、プール1億円かかります。小学生一人あたり1か月8万円程度の税金が遣われているそうです。税金を国民が納めることで、必要な公共施設の利用や公共サービスを受けることができます。これは、みんなが暮らしていく上で必要な社会生活に遣います。税金が無くなったら?火事や病気なった時に消防車や救急車が来ません。事件が起きた時に警察官が来ません。清掃車も来ないのでごみはそのまま、大変なことになります。6年生は、学習後に、「税金は必要なんだよ。」と、教えてくれました。税金の遣い道を決めるのは、選挙で選ばれた国の代表なので、18歳になって選挙権が与えられたら、適切に税金を遣える人に投票してほしいです。
最後に、1億円のレプリカを持たせていただきました。1億円の紙幣を持つことはなかなかありません。10kgの紙幣の束は重かったそうです。川崎南法人会の方々からは、6年生の話の聞き方や学習に向かうマナーがよいと褒めていただきました。
6月17日(火)
5・6年 体育「プール開き」


準備体操は念入りに 今日のシャワーは天国だ!


「エビカニクス」で水慣れ プールは気持ちいい


入水からけのび けのびでどこまで行けるかな
例年より1週間早いプール開きですが、絶好のプール日和となり、5・6年生が嬉しそうに、水泳の授業を楽しんでいました。3、4時間目は5・6年生、5,6時間目は3・4年生がプールに入りました。真面目な西みの子どもたち、「かぶとむし」の約束をきちんと守り、先生の話を聞いてどんどん水に慣れていきました。さすがです!
笑顔でプールから上がってくる子どもたちに、「今日の湯加減は?」と聞くと、「いい湯加減でした。」「最高!気持ちよかった!」と返答。「シャワーは、地獄のシャワーだった?」「ぜんぜん!天国のシャワーだった。」と、ご満悦でした。これから暑い日が続きます。気持ちがよい水泳学習ができることを願っています。
6月16日(月)
4年 国語「一つの花」


なぜ、お父さんはゆみ子に一輪の花を渡したのか


グループで考えを深める 各自、考えをまとめる
4年生は、今西祐行さんの名作「一つの花」の学習をしていました。今日の課題は、「なぜお父さんは、プラットフォームのはしっぽのごみすて場のような所に、わすれられたようにさいている花をゆみ子にわたしたのか」でした。お話の主題に迫る場面の学習に、先生も子どもたちも力が入ります。お父さんが戦争に行く時の極限状態の時の場面です。戦争のお話を自分事として考えるのは、難しくなってきました。子どもたちには、戦争下の状態を想像することが困難だからです。しかし、無意味な戦争は、二度と繰り返してはいけないことを知っていてほしいので、難しいことですが、忘れてほしくない問題として心に刻むよう、学習しています。
書かれている文章から、当時の悲惨な様子を想像します。わからないことは聞き、いろいろと考えていました。みんなの考えとして、「ゆみ子をあやすのを手伝いたかったから。」「ゆみ子に笑顔になってほしかったから。泣き顔をみたくない。」「大事にしてほしかったから。」「生きて帰ってこられない。」「もうゆみ子に会えないかも知れない。」とたくさん出されました。グループで意見交流をしたり、自分の考えをノートにまとめたりしていました。最後に「子どもの将来を心配しつつも、幸せを願う父親の思い」「花=命、命を大切にしてほしいと思う願い」に気づいていたようです。読めば読むほどわからなくなり、何度も書かれている文章を読み返し、発見できるお話は、名作として長く教科書に残ります。お話を読むとお父さんは戦争で亡くなっています。お母さんとゆみ子は二人ぐらしですが、戦争が終わり平和に暮らしていることがわかります。そのようなことは具体的には書かれていません。「それから、十年の年月がすぎました。ゆみ子のとんとんぶきの小さな家は、コスモスの花でいっぱいに包まれています。それから、、、。」素敵な文章で平和が訪れたことがわかります。
6月13日(金)
3年 総合「韓国となかよし」


韓国の挨拶「アンニョン」ペンイ(こま)を回す


楽器の使い方を伝授 好きな楽器で演奏


きれいな衣装にうっとり 次々に感想が飛び出す
今年も、「ふれあい館」の皆さんに来ていただき、3年生が、韓国・朝鮮の文化にふれました。「ハングルを楽しもう」では、簡単な会話とハングルを教えていただきました。目上の方に言う挨拶は、「アンニョンハセヨ」でも、お友達に言う時は、「アンニョン」、いつでもどこでも「アンニョン」。ありがとうは、「コマスミダ」。ハングル表を見ながら自分の名前もハングルで書きました。母音10と子音14で書き表すハングルは、効率的で最強だとつくづく思ってしまいます。
多目的ホールでは、コンギ(地面にコンギを広げて、1つのコンギを投げ、落ちてくる前に他のコンギを拾う遊び)、「ペンイ」(こま)、チェギチャギ(チェギを落とさないように蹴り続ける遊び)を夢中になって遊びました。
ACルームでは、農楽で使う楽器の「チャンゴ」、「プク」、「チン」の叩き方を教えていただき、「ケンガリ」のリズムに合わせて演奏をしました。「ケンガリ」に合わせて、大きくなったり、小さくなったり、遅くなったり、速くなったりと、同じリズムでも変化があるので、楽しく演奏できて、しばし、農楽の世界に浸りました。
教室では、民俗衣装のチマ・チョゴリ(女の子用)とパジ・チョゴリ(男の子用)の色の美しさに感激して、実際に着てみました。男の子、女の子にかかわらず、自分が好きな衣装を着る3年生は、「いいな。これこそ多様性!」だと思いました。
最後に、全員揃って体験の感想を話していました。韓国から日本に来た方から、「子どもが小学校に入学する時に困りました。でも、日本の方が親切に教えてくれました。ランドセルは韓国にはないんですよ。」「えー!」と驚きの声があがりました。「そう、みんなが当たり前に使っているものは、他の国にはないんだよ。」それぞれの文化の違いにもふれました。それぞれの国の素敵な文化を受け入れられる素敵な子の育ってほしいです!
6月12日(木)
6年 理科「植物のからだのはたらき」


植物を着色した水に入れたらどうなるのか実験


観察したことをノートに 葉まで色が着いている
6年生は、水やりした後の植物の変化を観て、植物の体の働きについて調べていました。植物を着色した水に入れて、植物の体の水の通り道を調べています。
実際に植物を目の前にして、肉眼で、ルーペを使ってよく観察しています。水の通り道は、「根が真っ赤で、茎は中側が赤い、葉にも赤い点々が付いている。」「根は、全体で水を吸っているんだね。」「茎は何本も真っ直ぐな線になっている。」「葉にも水は通っているんだよ。」「なぜ、葉は、点々なのかな。」いろいろな考察が話し合われ、全体で共有されています。自分の目で確かめることは新鮮で、6年生の興味を掻き立てます。観察したこと、気づいたことをノートにまとめていきます。
鮮明な写真や動画も子どもたちの思考に必要ですが、やはり実物を使っての実験や観察は、子どもたちに鮮明な思考を与えてくれます。そして、確かな知識を身につけてくれます。「根から吸い上げられた水分は、茎を通り、葉など全体に行き渡る。」「葉に行った水分はどうなるのかな?」次の実験に興味が出てきます。
6月11日(水)
6年 体育 「バスケットボール教室」


ボールを持たないでドン!ボールを持ってドン!


最後に試合を楽しみます 練習の成果が絶大!!


コーチたちとハイポーズ! 特別に!よい表情!
川崎ブレイブサンダースのコーチが来校しました。 1クラスずつ、ドリブル、パス、シュートの仕方を教えていただきました。教え方が上手なのはわかっていますが、たった1時間で、子どもたちが目をみはるほど上達しました。中でも、利き手にボールをのせて「出前」、もう一方の手を被せ「支える」、足を曲げ「小さくなって」、一気にジャンプ「ドン」、伸びた所をそのまま「キリン」のかけ声に合わせて行うと、ボールがポーンと遠くまで飛び、伸びがが違います。パスも力強くなり、遠くからのシュートも入りやすくなります。その後、試合をしましたが、お団子状態にならず、バスケットボールプレイヤーのようになって、みんなカッコよかったです。特にシュートをするときは、「出前、支える、小さくなって、ドン、キリン」を意識しながらボールを運んでいました。遠くからのシュートがいきなり入って、「オー!」と、自分自身に驚く子が続出しました。
教えていただいたコーチを囲んで記念写真を撮りました。みんな嬉しそうなよい表情をしていました。最後の片付けまでした子たちは、玄関の所でもコーチと写真を撮り、ご褒美となりました。本物にふれることは、学ぶ意欲になります。
6月10日(火)
2・3時間目 授業参観


栄養教諭による食育の授業 考え方が大事な算数


しっかり聞いてメモして いっしょに野菜の観察


どちらがいい?討論会 自由のために大切なこと
ご多用の中、また、雨で足元が悪い中を授業参観にご来校いただき、ありがとうございました。子どもたちは、お家の方々が来てくださるのを楽しみにしていました。どのクラスでも、真剣に勉強しています。にしみの子どもたちはよく勉強する子ばかりです。普段の様子を観ていただけたのではないでしょうか。少し違うのは、お家の方々に参加してもらえたことです。学校で頑張っている様子を観ていただけて、嬉しかったと思います。側で、「よくできたね!」と褒めてもらえて自信が持てたと思います。一緒に野菜の観察をしてもらえて、もっとお世話をしようと気持ちを新たにしたと思います。お家の方々の温かい眼差しと声かけが、にしみのよい子たちを育てているのだと思いました。お家でも、言葉にして、褒めていただきたいと思います。
6月9日(月)
5年 総合「にしみの”キラリ人”再発見」


西み1期生の多田さん青少年指導員の小山内さん


公園整備山科さん プロスノーボーダー今村さん


しっかりメモを取る5年生 話の後はハイポーズ
にしみのまちに住むキラリ人のインタビューが始まりました。今日は、4カ所に分かれて、たっぷりお話を聞きます。4名の方々は、懐かしそうに校舎内外を見回し、思い出話をしていらっしゃいました。5年生は、聞いてみたいことを次々と質問し、上手に深堀りしたインタビューをしていました。たくさんお話を聞いて、しっかりメモをとっていました。5年生は、聞いたお話をまとめて、みんなに教えてくれると思います。楽しみにしていてほしいです。
私も興味深いお話をお聞きして、知らないことがたくさんあり、びっくりしました。知らないことを知ることはなんて楽しいのだろうと思いました。例えば、西御幸小学校ができた頃は、第3公園から体育館くらいまで、大きなガラマン池があったそうです。子どもたちは、魚つりをして遊んでいたことや大きな魚がつれてさばいて食べたこと、池に落ちた子は誰もいなかったこと。今のわくわくプラザがある所には、「幸福山」があってすべって遊んだこと、子どもたちには「幸福山」だったけれど、親たちには、泥だらけになって帰ってくるので、「親不孝山」と呼ばれていたこと。はじめの校舎の屋根にはたくさん煙突が並んでいたこと。それは、石炭でたくストーブを教室で使っていたからだったこと。今のバスケットコートがある所は、木がたくさんあって森のようだった。つい最近までカブトムシがとれたこと。など、本当に驚きました。まだまだ、昔のびっくりすることがたくさんあるんじゃないかと思いました。
自分が住む学校やまちの昔のことや今自慢できることをお家の方や近所の方々に聞いて、知って、ますます学校やまちを好きな子になってほしいと思っています。
6月6日(金)
1・2・3年 集会「玉入れ大会」


集合して話を聞く1・2・3年生 ハッスル白組


体をたくさん動かして負けるな赤組 結果発表!
休み時間に、「スポーツ委員会」の人たちが、玉入れ大会を企画してくれました。今日は、1・2・3年生の玉入れ大会の日です。この日を楽しみにしていた低学年の人たちは、赤白帽子と水筒を持って体育館に集まりました。赤組と白組に分かれて座り、ルールをしっかり聞いていました。いよいよ勝負の始まりです。たまを拾っては投げ、拾っては投げ、思いっきり楽しみました。時間が来て終了!みんなでたまの数を数えます。みんながルールをしっかり守るので、短い時間の中で3回戦も行えました。片付けも勝負です。最後は、どちらが勝ったなんて、誰も気にせずに、「楽しかったね。」「たまをたくさん拾って、連続で投げたんだ!」「かごをねらったから、たくさん入ったよ。」と、低学年の子どもたちは嬉しそうに教室に戻って行きました。
片付けが終わると、「スポーツ委員会」のみんなが集まり、反省会です。「一人ひとりが何をしたらいいか考えて素早く動けていたのが素敵だったよ。」と先生から褒められていました。みんなのために役に立ちたいと思う5・6年生です。これからの活躍も楽しみになってきました!
6月5日(木)
4年 社会「地域で受けつがれてきたもの」


積極的に自分の意見を 祭りの移り変わりの資料


自己解決 資料から考える 考えを出し合い解決
4年生は、社会科の学習をしていました。「平塚の七夕まつりは70年間どのようにして続いてきたのだろうか?」の問題に対して、参加者のグラフや年表などの資料をもとに、考えを出し合っていました。「たくさんの人に支えられてきたのだと思うけど、どんな人が支えてきたのかな。」「商工会議所の人たちが中心になったって書いてあるよ。」「市民ボランティアも。」「外国の団体も加わったって。」「地元の小中学生のことも書いてある。」「僕たちみたいな小学生も力になったんだって。」「みんなが支えてきたから、市も協力したんじゃない。」たくさんの考えが出てきて、最後は、「平塚七夕まつりは、商店街や商工会議所の努力だけでなく、平塚市民や平塚市の協力もあって、今まで続いている。」とまとめていました。たくさんの人と言っても、それは誰か。2回目の少ない七夕飾り白黒写真から、回を重ねるごとに、盛大になっていく飾りの移り変わり、途中、中止の危機も乗り越え、地域で受け継がれているものがあることを知りました。
そういえば、私たちのまちにも、昔から今まで受け継がれている祭りがあります。小向八幡神社で毎年舞われている「小向獅子舞」です。「小向獅子舞」は、神奈川県無形民俗文化財」に指定されています。この誇れる祭りを受けついでいくのは、このまちに住む皆さんです。
6月4日(水)
2年 音楽「かえるのがっしょう」


鍵盤ハーモニカもお手の物 ドレミファミレド


列ごとに、指使いも滑らかに 楽しい音楽の時間
教室から、「かえるのがっしょう」の階名唱が聴こえてきました。6月の曲です。階名唱が終わると、鍵盤ハーモニカを出して、指使いの練習です。「1,2,3,4,3,2,1,」1番の指から続いておさえていきます。「ド、レ、ミ、ファ、ミ、レ、ド、」1番の指をミにずらして、「ミ、ファ、ソ、ラ、ソ、ファ、ミ、」またずらして、「ド、ド、ド、ド、」「ドド、レレ、ミミ、ファファ、ミ、レ、ド、」2年生は、とても上手に演奏します。「かえるのがっしょう」は、輪唱がおもしろい曲です。列ごとに順番に演奏していきます。「とても上手!なんでそんなに上手に吹けるの?」と先生に褒められて、ご満悦!何度も繰り返し輪唱を楽しんでいました。
「風になりたい」の歌も気持ちよく歌っていました。ミッキーマウスの声で楽しく歌っていました。
6月3日(火)
5年 総合「にしみの”きらり人”再発見」


にしみの”きらり人”に どんなことを聞こうか


せっかくの機会 インタビューを深堀りしよう!
にしみの”きらり人”を探し、来週、お話を聞く日にたどり着きました。インタビューをするのは難しいことで、限られた時間の中、その人しか知らないことを訪ねたり、その返答を予測して深堀りしたりしなければなりません。質問を書いていってそのことだけを聞く、一方通行では相手にとってはつまらなく失礼になります。是非、その人のことを調べ、インタビューの極意を身につけていってほしいと思います。
インタビューの内容をメモするのに、「フィッシュボーン」(魚の骨の形をしたメモ)を使っていました。一番上に聞きたいことを書き、返答を予想して、次のことを聞く、さらに、予想して、深いことを聞いていきます。魚の形をしたメモが適していると思いました。
6月9日、10日、12日、18日とインタビューの予定が入っています。インタビューの内容もそれぞれ、場所もいろいろ、誰に、どんなことを聞いたのか、後日、5年生に聞いてみたいと思っています。
6月 2日(月)
2年 生活科「1年生となかよし」


1年生と2回目の交流 もっと仲よくなるには


金曜日まで時間がない 1年生との遊びを考える
2年生は、生活科でもっと1年生と仲よくするためにはどうしたらよいか考えました。1回目の交流は教室でやりました。6月6日の2時間目は、場所を体育館、ワークスペース、廊下など広い場所を使って体を動かす遊びをしたら、もっと楽しいのではないかと考えていました。
遊びのバリエーションも少ないので、ぴかぴか班活動でやった活動を出し合い考えました。「たけのこニョッキって何?」「じゃんけんれっしゃは、盛り上がるね。」「だるまさんがころんだ、ペアだるまっていうのもあるよ。」「ドッジボールもいいね。」1年生に楽しんでもらおうと真剣です。
1年生となかよしのプリントに、遊びと場所を3つ書き、準備するものも書いていました。企画力が育っています。