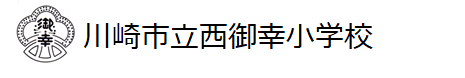7月 みんなの学校生活
7月20日(日)
公園清掃活動


除草も一苦労、頑張って 除草のBefore 除草のAfter


たくさん取れました! 充実感満載!記念撮影! お菓子をもらって大満足
児童25名、
7月18日(金)
全学年 夏休み前、授業終わりの日


1年生代表のお話 3年生代表のお話


5年生代表のお話 夏休みは、楽しみまーす!


充実した休みにします!よい表情で、元気でね!
夏休み前、授業終わりの日でした。「長ーい夏休みが始まります。夏休みにしかできないことを計画を立てて実行して、この夏休みはよく頑張ったな。最高だったな。と思える休みにしてきてください。そして、交通事故に合わないように、また、熱中症や病気にならないように、十分気をつけてください。」と、話をしました。
「夏休みの過ごし方」の後は、1・3・5年生の代表の発表がありました。「ぼくは、算数をいっぱい勉強して好きになりました。夏休みも勉強してもっとできるようになりたいです。」「ぼくが頑張ったのは、算数です。苦手だと思っていましたが、何度もやってみるとできるようになって、嬉しくなりました。今日で転校してしまいますが、むこうの学校でも、しっかり勉強したいです。」「4月からの4か月間、ぼくががんばったのは勉強です。特に、勉強が前の年と比べものにならないくらい好きになりました。まず、テストの点数があがりました。これは、家で予習をしたからです。次に、学習で積極的にコミュニケーションを取ることが多くなりました。それによって、自分の意見を目にも止まらぬ速さで広げることができたし、逆に意見を聞くとびっくりして声が出なくなるほど面白い意見や良い意見が飛び交ってとっても良い学習になりました。」これは、発表の一部分ですが、どの子も、一生懸命勉強してきたことがわかり、嬉しくなりました。
休み時間には、外で遊ぶことができました。使った場所の大掃除をして、給食を食べて、荷物を持って、下校です。家へと帰って行く子の表情は、みんなよい顔をしていました。4か月間やりきった充実感と明日からの夏休みの期待が笑顔となっていました。子どもたちが素敵な子に成長できたのも、充実した学校生活を送ることができたのも、保護者の皆様の温かいご協力とご支援のおかげだと深く感謝しております。心よりありがとうございました。夏休みの間、ご面倒をおかけしますが、それぞれの子どもたちが自分らしく成長できる機会となりますようによろしくお願いいたします。
7月17日(木)
2年 生活科「なつやさいピザパーティー」


好きな夏野菜を好きなだけ 注意して焼きます


「おいしそう!早く食べたい!」「いただきます」
みんなが育てた夏野菜が食べ頃に実り、餃子の皮を使って、ピザを作ります。身支度をして、手を洗いました。アルミホイルの上に、餃子の皮をのせて、ピザソースをぬって、好きな野菜とチーズをのせたらトースターで焼いてできあがり!2年生が育てた、ナス、ピーマン、オクラ、ミニトマト、新鮮な野菜です。好きなものだけを考えながらのせる子、山盛りにたっぷりのせている子、野菜で顔を作っている子、みんな、楽しみながら作っています。「できた!」それぞれオジリナルのピザができました。それから、トースターで皮が少し茶色に変わり、チーズが溶けたら出来上がり。「おいしそう!」「早く食べたいよぉ!」待ちきれない様子でした。全員が揃って、「いただきます!」「トマトは熱いから少し冷めてから食べるんだよ。」と声をかけ合っていました。
「モッチモチ!」「おいしい!」「餃子の皮でピザができるんだ。」と初めての経験に驚いている子と感想はまちまちでした。「もっと食べたい!」「もう一枚食べたい!」と素直な2年生が言っていましたが、「給食が食べられなくなっちゃうから、今日はこれでおしまい。」「簡単なので、夏休みのお昼ご飯にお家で作ってたくさん食べてね。」の声がけに、「はーい!」と元気な声が返ってきました。野菜もたっぷり取れるので、是非、夏休みの昼食にお試しください。準備も片付けも上手にできた2年生に花まるを贈ります。
7月16日(水)
3年 社会科「スーパーマーケット」


見学で知ったことをGIGA端末でまとめています


必要な資料を並べて 教え合いが始まりました
3年生は、スーパーマーケット「ライフ」に見学に行って、調べてきたことをGIGA端末でまとめていました。本格的にGIGA端末を使ってまとめるのは、初めてです。ワークシートに教科書、パンフレットをよく見て、何を知らせるか考えていました。中には、国語の教科書でまとめ方やローマ字入力のためのローマ字表を出している子もいて、自分が必要な資料がよくわかっていると感心しました。
スーパーマーケットは、品数が多く、1つのお店で物が揃うため、たくさんの人たちが買い物に行きます。見学では、普段見られないバックヤードを見たり、店長さんや定員さんに話を伺ったそうです。その中から、気になったことやものを、調べてわかったことやまとめを書いていきます。レポートのまとめ方を知るのは、大切なことです。子どもたちも、興味を持って、調べて入力していました。授業が進んでいくと、自主的な教え合いも始まりました。誰もが自分の課題がわかり、集中して学びに向かえる授業は、子どもたちの学習力を育みます。「夏休みは、タイピングを頑張るんだ!」と、こっそり教えてくれた子がたくさんいました。夏休み明けを楽しみにしています。
7月15日(火)
1年 生活科「うめぱーてぃー」


うめぱーてぃーの始まり始まり いただきます!


おいしい顔ってどんな顔 こんな顔!おいしそう
「ぼくたちがつけた梅ジュースができたので、梅ぱーてぃーに来てください。」とお誘いを受けたので、1年生の教室に行ってみました。ランチョンマットを敷いて、梅ジュースとヨーグルトに梅ジャムをのせて、「いただきまーす!」
梅ジュースを飲んで、「すっぱいけど、甘い!」「おいしい!」「元気になるんだよ。」「ヨーグルト好きじゃないけど、梅ジャムと一緒だったら食べられる。」「梅が苦手だけど、ぜんぜん食べられた!」と、自分たちが作った梅ジュースと梅ジャムが気に入った様子でした。梅の香りや味が残っていて、とってもおいしかったです。苦手だった子も食べられてよかったです。やっぱり、みんなと食べるとおいしいね!
「梅ジュースの後に残った梅を食べてみたい人?」「はーい!」何でも挑戦です。「梅あめおいしい!」「甘くておいしい!」1年生の梅ジュースと梅ジャム作りは大成功でした!
7月14日(月)
1年 音楽「どんぐりさんのおうち」


グループ発表もできます 指使いを覚えて練習


どの子も準備も素早く よい姿勢で演奏できます
3時間目は2組で、4時間目は1組で音楽の授業でした。音楽の準備は、鍵盤ハーモニカや歌集も揃えるので、準備や片付けは忙しいです。でも、1年生は、すっかり慣れて、準備も片付けも上手にできるようになりました。
今日の演奏は、「どんぐりさんのおうち」でした。「どんぐりさんの おうちはどこでしょう ふたつのおやまの ひだりがわ♫」「ドードードー」「そらまめさんの おうちはどこでしょう みっつのおやまに ききましょう♫」「ソーソーソー」と、鍵盤ハーモニカの「ド」と「ソ」の位置を確実に覚え、演奏の仕方(タンギングや指使い)を楽しみながら学べる曲です。
楽しそうに、歌を歌ったり、鍵盤ハーモニカで上手に演奏していました。先生に「上手!」と褒められて、とっても嬉しそうでした。かわいい1年生にぴったりの曲でした。
7月11日(金)
4年 総合「小向の獅子舞について調べよう」


小向獅子舞保存委員会の皆さん 獅子舞について


多くの質問にも答えて 熱心に聞き入る子たち
4年生は、自分たちが住む小向のまちに伝わる「小向の獅子舞」について調べ始めました。今日は、「小向獅子舞保存委員会」の方々が来校され、お話を伺う機会に恵まれました。4年生の子どもたちは、熱心にお話を聞き、メモをとっていました。
小向獅子舞は、このまちに300年以上も前から伝わる獅子舞で、川崎市の3大獅子舞の1つとして、民俗無形民俗文化財に指定されています。以前は、9月の八幡大神の例祭に披露されていました。今年は、10月の小向八幡神社の祭礼で舞われます。10月4日土曜日の夜は、「練り込み」といい、獅子舞に参加する全員が行列で町内を歩くそうです。5日日曜日の祭礼で獅子舞が披露されます。「大(おお)獅子」「中(なか)獅子」「女(め)獅子」の3頭の獅子と「仲立ち(なかだち)」が飛躍的に舞うそうです。それを笛や太鼓、唄やささらが囃し立てるそうです。獅子舞を見るのが今から楽しみになってきました。保存委員会の皆さんは、舞い手から獅子手まで、年齢に応じて継承してきたそうです。獅子頭をかぶせてもらうと病気をせず丈夫に育つと言われているため、たくさんの人たちが訪れて、獅子頭をかぶせていただくそうです。
4年生なりに調べて、自分が住むまちに伝わる獅子舞について知り、これからも継承していく担い手となる子が出てくるとよいと思っています。
7月10日(木)
5・6年「個別最適、自由進度学習」


授業の課題を確かめて自分のペースで学習をする


先生が進度を見ながら支援 自然と学び合いの輪


資料の読み込みも深め 最後はみんなで学び合い
本校では、それぞれのペースで学習を進められる自由進度学習を行っています。通常の学習の中で、自由進度学習が効果的な場面で行っています。自分のペースで進め、疑問が出たときには誰にでも聞きに行け、自分が集中できる場所を選んで自由な所で学習をしています。どの子もどのように学習を進めていったらよいか「学び方」を知っているので、効果が出ています。学習状況調査でも、各教科で成績が伸びています。
この日は、川崎市内の先生方が学習の様子を見に来てくださいました。1・2時間目の通常の授業時間です。5年生は、理科「台風と気象情報」、算数「小数のわり算」、6年生は、社会「東大寺の大仏はどんな目的でどうやって作られたのだろうか」、理科「生物どうしのつながりを考えよう」などの授業を参観されました。GIGA端末を使い慣れている子どもたちや先生方、資料や情報を分析している子どもたち、先生方の適切な支援、思考をフル回転して課題に取り組む子どもたちの様子、誰一人遊んでいる子がいなく集中している子どもたちの様子、に感動されていました。先生方は、日々の授業改善に熱心に取り組んでいます。
7月9日(水)
3年 図工「ちょうちんに楽しい絵をかこう」


「みんなが楽しくなる絵をかくよ。」力作ぞろい


思い思いの絵をかいて、完成!盆踊りで見てね!
小向西町町内会の盆踊りが、8月2日、3日の土、日曜日に行われます。町内会長の工藤さんと斎藤さんが、提灯をを学校に持って来てくださいました。わが校3年生と町内会のコラボレーションで、3年生がみんなが楽しくなるような絵を提灯にかいて、盆踊りの会場に飾られます。絵が得意な3年生は、主旨を聞いて、「かきたい!」「何をかこうか!」と盛り上がりました。そして、絵の具を取り出し、図工の時間に、提灯に絵をかいていました。思い思いの絵をかき、完成!素敵な提灯が出来上がりました!
出来上がった提灯は、廊下に展示しておきますので、懇談会の際にご覧ください。そして、町内会の盆踊りでは、明かりが灯りますので、また違った作品が見られると思います。是非、ご家族皆さんで、盆踊りに出かけ、3年生の作品である提灯を見てください。何より、ご家族皆さんで盆踊りを楽しんでください。
7月8日(火)
1年 図工「すなとつちとなかよし」


砂場に広がってすでにはだし 大きな川ができた


お団子作りだって得意 砂には水がすい込んでく
1年生は、汚れても大丈夫な服(万が一の時のために下着)やタオルを持ってきて、砂や土を使って造形遊びをしました。子どもたちは、砂や土の感触を楽しみながら、山やトンネル、川など、夢中になって、思い思いの作品を友だちと協力して作っていました。何も言わなくても、すぐに裸足になって、地面を踏みしめていました。深く掘った所に水を入れて、「川ができた!」と喜んでいました。でも、あっという間に砂に水がすい込まれていき様子を見て、下を固めたり、水をたくさん入れたり、工夫していました。どろ団子もとっても上手に作っています。砂をヨーグルトのカップに入れて「はい、ヨーグルトをどうぞ。」とすすめてくれました。見立ても上手です。汚れてもよいなんて、なかなかこんな楽しいことは滅多にありません。子どもたちは遊びを通して学びを深める貴重な体験となりました。
7月7日(月)
3年 道徳「生きている仲間」


育てたことがある植物は 黒板にいっぱい出され


同じ経験をした人は? 「いただきます」の意味?
3年生は、道徳の授業で「生きている仲間」の勉強をしていました。自分が育てたことのある植物を先生が聞くと、どんどん手が挙がり、黒板にいっぱい書き出されていました。お話を読み、最後に「いただきますには、どんな意味があるんだろう」ということを考えていました。
ミライシードに書き綴った文章を紹介します。「植物も同じ生き物だから、自分も生き物を育てる時は、植物の気持ちも考えるようにする。」「いっしょに育ってきてくれた植物にかんしゃを伝えるために「いただきます」を言うんだと思います。」「作った人にありがとうの気持ちで言う言葉だと思います。」「人は食べないと死んじゃうから人が作った食べ物に感謝して食べるからいただきますがある。」「生きている命を犠牲にして食べるから命と作った人に感謝する。」など、よく考えて、自分の考えを書いていました。とっても充実した1時間となったようです。
7月4日(金)
2年 生活科「生きものとなかよし」


あっちの方に行ったら 草むらで虫を探す2年生


ビオトープには何かいるぞ バッタを捕まえたよ
2年生は、これまでの経験や聞いたり調べたりしたことをもとにして、生き物のいる場所を予想しながら探していました。「湿った石の下に、ダンゴムシがいるよ。」「草の中には、バッタがいそう。」「葉っぱの裏にチョウチョがいるかも。」「ビオトープには、水の生き物がいるんじゃない。」と、それぞれが校庭のあちらこちらに散らばって、虫を探したり、捕まえたり、観察したりしていました。
1時間もすると、それぞれの虫かごの中には、ダンゴムシやショウリョウバッタ、ヤゴなどが入っていました。観察してみたい、飼ってみたい生き物を持ち寄り、観察してもとの場所に戻したり、すみやすい棲家を作ったりしていました。生き物をあつかう勉強です。生き物の成長の様子や自分ができるようになったことにきづけるようにしていってほしいです。でも、やはり生き物も、すみなれた場所が一番だと思います。元気がなくなってきたらもとの場所に戻してあげることも必要です。生き物の命を大事にする子でいてくださいね。
7月3日(木)
4年 社会科「ごみはどこへ」


ごみ収集車のごみは清掃工場へ運ばれ燃やされる


わかったことをメモ 集中してまとめている
家庭からでるごみは、ごみ収集車によって清掃工場へ運ばれます。清掃工場での処理の仕方の動画を見ながら、予想と合っていたか確認していました。王禅寺の清掃工場の様子です。収集車から落とされたごみは、集められクレーンで焼却炉の中に落とされ、900℃の高温で燃やされ、灰になります。「匂いが漏れないようにエアカーテンがあるんだって。」「クレーンゲームみたいだけど、汚そう。」「すごい量のごみだね。」「高温で燃やすと、匂いがなくなるんだって。」「1日に500tから600tも集められるんだって。想像できない。」「きれいな灰になった。」「灰は、運ばれて浮島の埋立地でうめられるんだって。」「えっ、あと30年で埋立地はいっぱいになるんだ。」「俺たちが40歳になったら、どこに捨てるんだ?」「やばくない。」見学できない所まで見られるのが動画のよい点です。驚きがいっぱいです。「だから、ごみを分別したり、少なくしたりして、30年より伸ばすんだね。」動画を見ながら頭をフル回転、よいことに気が付きました。ごみは燃やしても無くなるわけではありません。たっぷり勉強して、次時は、「ごみを少なくするにはどうしたらよいのだろう」の学習へと続くと思います。よく考え、よく調べ、自分の考えをもつ、賢い4年生でした。6時間目の授業、今日も一日、しっかりと勉強しました。大変よくできました!
7月2日(水)
1年 生活科「アサガオのつぼみのかんさつ」


アサガオが大きくなりました 上手に書けたね


つぼみだけをよく見て 小さいつぼみがいっぱい
1年生が毎日水やりをかかさず行うので、アサガオがフサフサと大きくなりました。紫色や赤紫色、薄紫色、ピンク色の大きな花も咲き始めています。自分の背丈位大きくなったので、観察カードに全部を書くのは難しいし、花も葉も小さくなって、よくわからなくなってしまいます。そこで、よく見る視点を決めて観察をします。今日の視点は、「つぼみ」です。たくさんあるつぼみの中から選んで書きます。先が尖っていて、真ん中が膨らんでいます。つぼみは、時計回り(右回り)に巻いていることに気付いたかな?よく見て、さわってみて、観察カードに詳しく書いていきます。「つぼみは、さわるとふわふわです。」「ザラザラです。」「ぽわぽわです。」手の感じ方はみんな違うんです。他にも、「まわりには、やわらかいけがはえています。」「ぼくのつぼみは、ふくらんでいるので、あしたさきそうです。」「つるのさきには、あかちゃんのつぼみがいっぱいあります。」と観察カードに書いていました。じっと見て、変化を見つけているのは、小さな植物博士そのものです。