国際科ニュース
2026/2/6 国際科2年生 NEC Future Creation プログラム ✕ 総合探究学習 発表【2026年 2月6日(金) NEC Future Creation Program ✕ 総合探究学習 発表】
国際科2年生は夏休み明けから、昨年度に引き続き、「できたらすごい社会を創る」を目標に、NEC Future Creation プログラムの方々と共に探究学習を進めてきました。生徒たちは、同じ方向性に興味関心を持つ仲間とグループを作り、「AIの有効的な活用」「こどもの平等な教育の機会」「海洋の環境保護」「教員の働き方改革」「ショート動画が子供に与える影響」「現代の食」「川崎市(地域創生)」「共生~ストレスのない社会~」の8班に分かれ活動を進めてきました。探究学習を通し、約半年間、NEC社員のみなさまにアドバイザーとしてご協力をいただきました。10月にはNEC本社ビルを訪問させていただき対面で、11月にはオンラインでディスカッションをさせていただき、アドバイザーの社員のみなさまからご助言をいただきながら探究学習に取り組んできました。
探究学習の集大成として、各班、取り組んできた探究課題に対し、英語によるプレゼンテーションを実施しました。生徒たちは、冬休み前までに英語による発表準備、冬休み明けからは発表スライド準備、とNEC社員のみなさまのみならず、本校ALTの大きなサポートに支えられながら準備を進めてきました。発表当日には、アドバイザーを務めてくださったNEC社員のみなさまの中から11名の方々にご来校いただきました。発表を参観いただいた社員のみなさまからは、「今回経験したことが終わりではなく、将来につなげてほしい。これから先、今の考えや意見を変えることが必要なときもある。とても勇気がいることだが、前に進むためには必要なこと。」「調べるだけではなく、実際に話を聞く・参加して実践してみる、など課題解決のために深く取り組んでいる班もあってよかった。」「答えのない問い。ココに取り組むプロセスが社会では重要になってくる。今回の経験を大切にしてほしい。」など、国際科の生徒が3年生で取り組む課題研究につながる貴重なご意見をいただきました。今年度の探究学習を通して得た気づきを次年度に活かしてほしいと願っています。
2026/2/6 高大連携 東京外国語大学の学生さんによる国際理解ワークショップ
2月6日(金)5・6校時に、国際科1年生を対象として、東京外国語大学「国際理解さーくる くらふと」の皆さんによる貿易ゲームのワークショップを実施していただきました。この活動では、各グループが国や地域の立場になりきり、限られた資源や条件のもとで交渉や貿易を行いました。ゲームを通して、生徒たちは国ごとに置かれた状況の違いや、交渉力・情報量の差が結果に大きく影響することを体験的に学びました。活動後のディスカッションでは、「現地の人のためになる発展途上国への支援はどのようなものがあるだろうか」という問いについて、さまざまな意見を出し合い、考えを深めることができました。

2026/1/29 オンライン国際交流プログラム With The World
With The Worldさんにご提供いただいている「オンライン国際交流授業プログラム」を国際科1年生と2年生で実施しました。
今年度は12月に1年生、1月に2年生がオンライン国際交流授業に参加をしました。
今回1年生は、
2年生は、インドやパキスタンの学生とオンラインでの交流を実施




*今回の交流活動が2/6タウンニュース 中原区版に掲載されました。
https://www.townnews.co.jp/0204/2026/02/06/823809.html
With The World HP:https://withtheworld.co/
2026/1/22 国際科1・2年生 第2回 ALT Day 実施
橘高校国際科では年に2回、約20名のALTをお迎えし、英語でコミュニケーションを図る機会を設けています。今回は20名のALTの方々をお迎えし活動しました。
国際科2年生は今までの学習や経験を通して実践的に身につけたspeaking skillを活かし、Free Conversationに取り組みました。何もトピックが準備されていない中、始まりの一瞬こそ緊張した様子でしたが、どのグループも積極的にALTの方々とやり取りをしている様子でした。誰かのサポートがなくても自分たちで考え、その場の状況に応じて判断し活動している姿に大きな成長を感じました。
国際科1年生はサイコロトークに取り組みました。トピックリストからランダムに選ばれたトピックを基本に、積極的に会話を続けることができました。普段以上に輝いた目で活動に取り組んだ後には、活動の終わりを惜しむ姿が見られました。「伝えたい」「交流したい」という気持ちで活動に取り組む素敵な機会となったと同時に、やりとりを続けるうえで大切なスキルを身に付けることができる良い機会となりました。


2025/12/24 川崎市の姉妹都市である韓国富川市の高校生との交流
韓国富川市の高校生10名と富川市コリウル青少年センター等のスタッフの方々7名が来校しました。高校生10名は国際科2年生の専門外国語の韓国語の授業に参加したあと、全校集会で紹介され、日韓の友好を願う素晴らしいスピーチを行いました。最後に食堂で国際科2年生とランチ交流を行いました。たくさんの笑顔と、日本語・韓国語・英語が飛び交い、若い世代の日韓の絆が育まれました。

2025/12/1 国際科課題研究発表会
国際科3年生が1,2年生に向けて世界の課題の解決策を探究した成果を発表する会が行われました。国際科での3年間の学びの集大成として、4月から調査・研究してきたことを英語で発表しました。聴き手の心に響くような工夫を凝らし、世界の様々な課題の解決について熱い思いが伝わる素晴らしい発表でした。今年の3年生が自ら決めて探究した9つのテーマと、感想を以下に抜粋しましたのでご一読ください。
![]() 国際科課題研究のテーマと感想の抜粋.pdf [ 144 KB pdfファイル]
国際科課題研究のテーマと感想の抜粋.pdf [ 144 KB pdfファイル]
2025/12/10 国際科1・2年生 ミャンマーワークショップ
ベトナム・ミャンマー教育支援学生団体「JUNKO Association」に所属している、明治学院大学の学生さんを7名お招きし、ミャンマーに関してのワークショップを実施していただきました。
1年生は、ミャンマーの学校生活について学んだあと、オリジナルワークシートを用いて日本とミャンマーの教育の違いについてグループでディスカッションをしました。「学校の成績はテストの点数だけでつけるの?」や「ミャンマーの大学進学率は?」など、日頃、ミャンマーに触れる機会が多くない中で、同国の教育の現状や社会情勢について生の声を聞くことができた、大変貴重な学びの時間となりました。
2年生は、これまでのワークショップで培ってきた知識や情報を踏まえ、ミャンマーとの交流企画の立案に取り組みました。「学校生活の疑似体験」や「自国の文化クイズを交えた何でもバスケット」、「縁日体験」など、どのグループも来日するミャンマーの小中学生が日本をより楽しく学べるよう工夫を凝らしながら、企画書を完成させました。今回のワークショップを通して、自分たちにどんな支援ができるかを考えるきっかけになるいい機会となりました。
JUNKO Associationの皆さん、今年度もありがとうございました。


2025/11/13(木)第2回国際理解講演会
11月13日、国際科1年生から3年生対象に第2回国際理解講演会を実施しました。今回はペシャワール会に所属されている、梅本霊邦氏を講師にお迎えしました。アフガニスタンの地で医師の中村哲さんとともに用水路建設に携わってこられた梅本氏より、現地の声や中村哲さんの生のことばを聞くことができました。
【生徒の感想の一部を紹介します】
・講演会を通して、改めて中村医師の当時持っていた意志の強さを知りました。事前に私たちが教科書で学んだときには知らなかった現実の過酷さや苦労があったということを知り、医師としてのプライドもありながら自信と勇気を持って用水路建設に着手し、作り上げたことは本当にすごいことだと感じました。
・本日の講演をお聞きして、改めて平和とは何かということに関して自分の考えを深めることができました。中村さんの用水路建設に対する計り知れないほどの責任感と本気度を非常に感じることができ、また、力強い言葉の裏にある性格とアフガニスタンへの思いも感じ、胸をうたれました。今回の学びを今後の生活にもつなげ、自分にできることを探していきたいです。

2025/10/23(木) 外務省出張高校講座・座談会
現在、外務省 総合外交政策局 国際平和協力室で勤務しておられる小日向みなみ氏を講師としてお
講演会に参加した生徒からは、



2025/10/20 国際理解・国際協力のための高校生の主張コンクール
外務省・日本国際連合協会主催「国際理解・国際協力のための高校生の主張コンクール」に、神奈川県代表で本校の1年国際科より生徒1名が出場しました。この主張コンクールは、高校生が国際連合や国際社会が抱える課題について自ら考え、国際理解・国際協力の重要性を発信することを目的として毎年開催されています。
今年は国連創設80周年という節目の年であり、「分断や対立が深まる中、国連が国際社会の利益に応えるために必要なことは何か」などを題材に、全国から多くの応募が寄せられました。本校生徒は、神奈川県代表として「教室から始める難民支援」をテーマに、自分たちの学校生活に根ざした視点から、日常の学びや行動が国際協力につながることを堂々と訴えました。

2025/10/09 PM 東京ジャーミイ・ディヤーナト トルコ文化センター訪問
スペシャルウィーク最終日の午後は、渋谷区にある東京ジャーミイ・ディヤーナト トルコ文化センターを訪問いたしました。日本最大のモスクがあるこの施設で、女子は初めてのヒジャブを身にまとい、モスク内を見学しました。イスラム教徒の教えや考え方、歴史について講座を通して学び、異なる宗教を肌で感じることで、多文化共生社会への理解を深めることができました。
2025/10/09 AM JICA 地球ひろば訪問
スペシャルウィーク最終日の午前は、市ヶ谷にあるJICA 地球広場を訪問いたしました。体験ゾーンでは開発途上国の実情について学び、多文化への理解を深めました。また、交流ゾーンでは、ウガンダにてJICA海外協力隊として活躍された方の体験談を伺いました。Q&Aでは、海外協力隊として活動する中での困難ややりがい、バックパッカーとして世界一周を果たした体験についてなど様々な質問がされました。この経験を通して、単に開発途上国の現状を知るだけでなく、「世界はつながっている」という意識を強く持つことができました。

2025/10/08 国際科2年生探究学習 NEC本社ビル訪問
国際科2年生は夏休み明けから、NEC Future Creation プログラムにご参加の社員の皆さまにご協力いただき、後期探究学習に取り組んでいます。
オンライン上で社員の方々からサポートを受け学習に取り組んでいますが、この度NEC本社ビル訪問が実現し、オンラインでご協力いただいた社員の方と対面で活動をさせていただきました。各グループ探究している内容について社員の方々とのディスカッションの場を設けていただきました。全体での意見交換の中で生徒からは、「課題に取り組む際、自分視点ではなく相手視点で物事をとらえることが大切。」「調べたつもりでも、現状把握が不十分であったことに気づいた。」「物事を細分化して考えるスキルを学ぶことができた。」などの意見が出ました。社員の方からは、「テーマがまだ粗削りである。深掘りが必要。」「色々な視点から世の中をよくしていこうと高校生が考えている事を知れて、日本の未来は明るい!と感じた。」などのお言葉をいただきました。
国際科2年生は今後、各グループのテーマに沿った探求内容をブラッシュアップし、2月上旬に予定している英語による学習発表へ向け引き続き学習に取り組んでいく予定です。



2025/10/08 AM おいしい国際理解
スペシャルウィーク3日目の午前は、日頃よりお世話になっている韓国語・中国語の先生方と一緒に韓国料理と中華料理を調理いたしました。「料理」という体験を通して、文化の違いに気づき、理解を深める貴重な機会となりました。
2025/10/07 Tokyo Global Gateway (TGG)での一日英語研修を実施
スペシャルウィーク2日目は、Tokyo Global Gateway(青海)にて一日英語研修を実施いたしました。「演劇」「身近な買い物からSDGs目標12について学ぼう」「マーケティング」「ニュース取材体験」の4つのプログラムに参加し、実社会で求められる英語を学びました。英語を使うことに対して積極的な生徒たちは、終始、自分の考えや気持ちを英語で伝えようと活発に活動していました。この研修を通じて、今後のキャリア形成への意識が一層高まりました。


2025/10/06 PM実施 通訳講座
スペシャルウィーク初日は、午前と午後、それぞれ講演会を1つずつ実施しました。午後は、日本会議通訳者協会に所属し、アウトリーチ活動をされている3名の方を講師としてお招きし、「通訳の仕事について」と「通訳スキルは英語の勉強にも役立つ?!!!」、「プロ通訳が使用する機器に触れてみよう!!逐次通訳&同時通訳体験」を実施しました。
【講演会の最後に生徒たちから講師の方々への質問コーナーでた内容とお答えいただいた内容の一部を紹介させていただきます。】
Q. AIが発達しているが、通訳の仕事は今後、どのような影響があると感じていますか?
A. 通訳の仕事が減っているとは感じません。AIに関する会社関係の通訳の仕事が増えていると感じています。
気持ち、思いをを伝える通訳としては、すべてAI通訳になるとは思いません。伝承で伝わっているもの、空気・話者の雰囲気を読み取り、伝える事ができるのは人間通訳でしかできないと考えています。また、それらをデジタル変換するのは難しく、人間通訳にしかできないことなのではないだろうか。と思っています。
Q. 通訳の勉強、体力も大変そう。やりがいは何ですか?
A.「職人技」「伝わった」を実感することで「生きてる!」と感じるんです!!様々な会社のトップ(経営陣)の話を聞けるのは、会社に務めている役職のついていない一般の社員ではできないこと。企業のトップが話す内容はものすごく好奇心が掻き立てられ、毎回驚きの連続、新たな発見が新鮮です。
Q. 言葉を通訳するだけでなく、空気、雰囲気を読み取って伝えることも通訳をする上で大切だと思います。文化背景なども学ぶように心がけているのですか?
A. どのような内容を通訳するかによって、国という大きなカテゴリーだけではなく、そのチームの文化、会社内の文化、オープンマインドを心がけることを大切にしています。
Q .一番緊張した通訳は?
A. 「今上天皇の通訳を務めさせていただいたとき」、「商品が売れないと、その商品の取扱いがなくなってしまう…という重責を担ったテレビショッピングでの通訳を任されたとき。」「初めての通訳の仕事の日、プロ通訳初日にも関わらず、ベテラン通訳だと思われたこと。」
2025/10/06 AM実施 多文化共生ワークショップ(東京外国語大学 国際理解教育サークルくらふと)
第1日目である10/6(月)は、多文化共生ワークショップを東京外国語大学の学生さんを3名お招きし実施しました。
外国にルーツを持つ学生をモデルに、外国の方が日本で生活をしていく上で、どのような困りごとを抱え、何が障壁になっているのか。誰にとってもやさしい「共生社会」はどうしたら築けるのか。大学生の方々のサポートを受けながら一緒に考え、自分たちでもできる身近なことを探っていくワークショップに取り組みました。
【ワークショップの中で生徒から出た意見を一部紹介させていただきます。】
・本人の困り事がどこにあるのかを知り、どのようなサポートが必要なのかを探ることが大切なのでは。
・外国の方々が生まれ育ったバックグラウンドを知らないと、気づかないうちに傷つけてしまうことがある。
・自分にとっての当たり前でも、外国の方にとってはわからないこともあるので、友達同士で「今のわかった?」など確認をすることも大切なのでは。
・地域の中で海外の方が参加できる催しを企画するのもよいのでは。お互いに分かりあえる場があれば、困りごとも共有できると思う。
2025/10/06-09 スペシャル ウィーク(専門学科の特色を生かした特別活動週間)
普通科の生徒が修学旅行期間中である10/6(月)~10/9(木)、国際科2年生は、この期間をスペシャルウィーク実施期間として校内外で専門学科の特色を生かした学びを実施いたしました。
| 日程・実施場所 | 実施内容 | 講師 |
|
第1日(10/6[月]) 校内 |
AM: 多文化共生ワークショップ PM: 通訳講座 |
AM: 東京外国語大学 国際理解教育サークル くらふと PM: 日本会議通訳者協会 |
|
第2日(10/7[火]) Tokyo Global Gateway Blue Ocean(青海) |
終日: 英語研修 | 終日: イングリッシュ スピーカー 外国人講師 |
|
第3日(10/8[水]) AM: 校内 PM: NEC本社ビル |
AM: おいしい国際理解 PM: 探究活動 |
AM: 本校中国語講師、韓国語講師 PM: NEC社員(Future Creation プログラム) |
|
第4日(10/9[木]) AM: JICA 地球 ひろば PM: 東京ジャーミィ |
AM: 展示見学 / JICA海外協力隊体験に基づくお話 PM: 施設見学 |
AM: JICA 施設スタッフ PM: 施設ガイド |
2025/09/13-14 玉川さんと座談会(13日) Stanford e-Kawasaki対面講座(14日)
9月13日、橘高校にStanford e-Kawasakiの講師を務める玉川さんが来校されました。座談会では、去年の受講生からアドバイスをいただき、今年受講する生徒にとって、これから半年間続く講義への思いを再確認する貴重な時間となりました。

翌14日には、同プログラムの第一講義が対面で実施されました。米国スタンフォード大学のGary博士がディレクターを務める「Stanford Program on International and Cross-Cultural Education (SPICE) 」の講義に生徒は興味津々でした。講義終了後も、積極的に質問を行い、この貴重な時間を有意義に過ごしていました。
市立川崎高校の生徒たちとのグループワークでは、最初は少し緊張しながらも、ディスカッションが始まると、お互いに英語で意見を伝えようとする熱心な姿勢が見られました。

- 今年の夏に行われたStanford e-Kawasakiの表彰式がSPICEのHPに掲載されました。
2025/08/30 スタンフォード開講式
本校国際科の生徒10名が、今年も川崎市とスタンフォード大学の共同事業「Stanford e-Kawasaki」にオンラインで参加します。
開講式では生徒一人ひとりがこのプログラムに対する意気込みを英語で発表してくれました。今後、半年間にわたり毎月オンラインでスタンフォード大学の授業に参加し、多様性やアントレプレナーシップへの理解を深めていき、来年3月にはプレゼンテーション発表会を行います。

2025/08/14-25 国際科2年生AUS海外研修
「グローバルな未来へ、確かな一歩!」
2025年8月14日から25日の12日間、国際科の生徒たちが海外研修でオーストラリアを訪れました。多文化国家であるオーストラリアは、日本とは違う習慣や文化で溢れており、生徒は見るもの聞くものすべてに心を躍らせていました。現地の学校では、積極的に交流を深めることで、日本とは違う価値観を学び、グローバルな視野を大きく広げることができたようです。

【生徒の感想】
・授業では積極的に発言したり、現地の子にも話しかけたりでき、なにか殻を破れた気がする。日本にいるといろんなことが気になってしまうけど、何も気にせずに純粋に会話を楽しむことができた。ホストファミリーには感謝しきれないほどお世話になった。いつかもっと上達した英語力で成長した自分を見せにまた会いに行きたい。
・最初から最後まで新鮮な気持ちで本当に一日一日が充実していて楽しかった。英語は普段触れる機会が多いけど、現地では、ずっと英語で質疑応答をしなくてはいけなかったから毎日頭をフル回転させてたなって思う。会話のキャッチボールができたときは本当の海外に触れてる感じがして嬉しかった。自分が知ってる単語を組み合わせたり、文を作ったりしても伝わらない時があるからやっぱたくさん喋って経験を積むことが大切なんだなと思った。いろいろ困難なこともあったけどそれも含めて全部大切な思い出だなと思う。そして最後に、本当に食べ物がおいしかった!!!
・初めてのオーストラリアだったから上手くいくかなと不安な気持ちで行きました。だけど、出会った人たちみんなほんとに優しくて、いっぱい話しかけてくれて、すごく嬉しかったし、自分も日本の文化を伝えることができたので良かったなと今は思います。あと多文化の日(OPA Vision performance)があってそこで生徒が自分のルーツの国の衣装を身につけてパフォーマンスとかもしてるのを見て、すごいなと思ったし、オーストラリアは多文化理解について学ぶのにぴったりな場所だなと感じました。
・行く前は本当に不安で仕方なかったけれど、ホストファミリーや友達と過ごしたり、オーストラリアの観光ができたりした経験は絶対に今後の自信につながっていくと思う。親から10日間も離れて自分の力でコミュニケーションを取ったのがたのしかった。絶対にまたオーストラリアに戻りたいです!

2025/7/11 国際科1・2年生 ミャンマーワークショップ実施
ベトナム・ミャンマー教育支援学生団体「JUNKO Association」に所属している、明治学院大学の学生さんを4名お招きし、ミャンマーに関してのワークショップを主催していただきました。
1年生は、初めてミャンマーについて学ぶ機会となりました。国の情勢、食や文化などの紹介を聞いたあと、オリジナルワークシートを用いて「ミャンマーの文化について調べてみよう」というワークショップに取り組みました。伝統衣装、舞踊、宗教、住まいなどさまざまなテーマでそれぞれが調べた内容をグループで共有し、新たな発見がたくさんありました。
2年生は、今年度2回目のワークショップになりました。ミャンマーの文化的特徴や、人々の生活の中に仏教の教が浸透しているため、日本とは異なるマナーがあることなどを学びました。2年生の生徒たちは、グループワーク「日本とミャンマーの違いを見つけよう」に取り組み、各自が感じたことをグループ内で共有しました。「日常生活で民族衣装をよく身につけている。」「スパイスを効かせた食べ物やフルーツが豊富で美味しそう!!」などミャンマーへ興味を抱くきっかけとなるよい機会となりました。
JICA×橘高校国際科ニュース
1.JICAエッセイコンテスト特別学校賞受賞
国際科では、毎年夏休みに国際科1・2年生の全員がJICA国際協力中学生・高校生エッセイコンテストに応募しています。
この生徒たちが国際協力について真摯に考える取り組みが評価され、JICAより特別学校賞を頂きました。
昨年度の優秀作品集の28ページに本校の取り組みが紹介されていますのでご覧ください。
2.卒業生2名がJICA海外協力隊に合格し、2024年夏より1名がマラウイへ、もう1名がジンバブエに派遣され活躍しています。


彼女たちの言葉が、高校時代にJICAエッセイコンテストに取り組んでいたことを振り返る「感謝の手紙」に掲載されました。
以下のリンクより7ページと12ページをご覧ください。
https://www.jica.go.jp/cooperation/experience/essay/__icsFiles/afieldfile/2025/04/24/letter.pdf
3.JICA「世界の笑顔のために」プログラムに昨年度の3年国際科がクラスで参加し、お礼状がと子どもたちからの手紙が
ウガンダのIN NEED HOMEより届きました。昨年度、文化祭の売上金を寄付し、使わなくなったリコーダーやピアニカを集めて送りました。
手紙のやり取りや、オンラインでの交流も行い、遠いアフリカのウガンダの子どもたちと心の通う交流ができました。
感謝状と手紙はこちらからご覧ください。
![]() ウガンダよりお礼状.pdf [ 845 KB pdfファイル]
ウガンダよりお礼状.pdf [ 845 KB pdfファイル]![]() ウガンダの子どもたちからの手紙.pdf [ 1504 KB pdfファイル]
ウガンダの子どもたちからの手紙.pdf [ 1504 KB pdfファイル]
2025/7/4 UNICEF HOUSE 訪問
7月4日金曜日、国際科1年生が国際理解教育の一環として品川にあるUNICEF HOUSEを訪問しました。生徒たちは、4グループに分かれて、ボランティアガイドの方々と共に施設内を見学しました。保健・栄養・水と衛生・教育などの活動で世界の子どもの命と未来を守っているユニセフ協会。リアルな世界の実情をダイレクトに伝える展示物は、世界の子どもたちが置かれている困難な状況を体験的に学ぶことができました。この訪問を通じて得られたものを今後の国際理解教育の活動に活かし、1人でも多くの世界で困っている方々を助けてほしいと考えています。


2025/6/26 ALT DAY
6月26日木曜日、ALTを20名ほど招いて、国際科1、2、3年生とICC(国際交流部)が交流を行いました。1年生はサイコロトークで英会話を、2年生は8月にオーストラリア海外研修の際に現地の学校で行う日本文化紹介を、3年生は英検準1級の面接練習の後フリートークを楽しみました。放課後はICC部でも小グループでトピック・ディスカッションを行いました。生徒2,3人にALT2名という恵まれた環境で、英語を使って表現する楽しさを実感するとともに、「もっと英語でコミュニケーションが取れるようになりたい!」と、今後の英語学習へのモチベーション・アップにつながりました。
2025/6/12 2025年 第1回国際理解講演会
6月12日、第1回国際理解講演会を実施し、国際科1年生から3年生の全学年の生徒が参加しました。昨年、2024年ノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会(被団協)の事務局次長を務める和田征子氏を講師にお迎えしました。核兵器廃絶と原爆被害者への国家補償を二つの柱に掲げて活動をしている被団協の方々の様々な取り組み、和田さんのお母様から受け継いだ貴重なお話しについて講演をしていただきました。
【生徒の感想の一部を紹介します】
●講師の和田さんが1歳のときに被爆された当時、お母様が24歳の若さだったということにとても驚きました。お母様が1歳の幼子を抱えながら、他にも被爆にあった方々の手当をしていたとのお話をきき、自分が24歳で子育てもしながら、そんな事ができるのか。今の私にはとても想像できないほど過酷な状況だったのだろうと 思いました。
●原爆について、ニュースや授業で聞いたり、調べたりしたことはあったけれど、今回、和田さんから直接お話し を聴き、真の原爆の恐ろしさ、被害の大きさを実感しました。それは、私の想像できる域を超えている内容で衝撃を受けました。現在、被爆者の方々の高齢化が進む中、私達若い世代が、原爆がもたらす恐ろしさ、残酷さを次の世代に伝え続けていく役目を国内外問わず担い続けていかなければならないと強く感じました。
●戦後多くの人々が動き出し、少しずつ世界の核に対する考え方が変わりつつあることに希望を感じました。被爆者 が自らの経験を通して、世界に訴えるために被団協を結成し、70年間前に進み続けるこの思いを、被爆者の子孫、 国民として、私たちが受け継いでいくべきだと考えます。兵器ではなく、言葉で伝える。インターネットが普及し た今だからこそ、世界中の人々と言葉を交わすことを大事にして、より身近に感じるべきだと思います。
【グループワークの際、生徒たちが考えた質問内容の一部を掲載させていただきます】

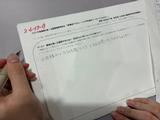

2025/6/9 姉妹都市米国ボルチモアのMorgan State Universityとの交流
川崎市の姉妹都市のひとつである米国ボルチモアにありますMorgan State Universityから、教授と学生さん達合計25名が本校を訪問し交流しました。国際科1年生による日本文化紹介、国際科3年生は課題研究で班ごとに探究している国際問題についての意見交換を行いました。また、スポーツ科3年生が校舎案内を行い、自分たちで作ったJapan Guide Bookを贈りました。アメリカの大学生との交流は日ごろ学んでいる英語を使ってコミュニケーションをする機会でもあり、異文化を超え理解しあえる喜びを実感する素晴らしい機会となりました。川崎市のHPにもニュースとして掲載されていますのでこちらのリンクからご覧ください。https://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000177582.html
2025/6/6 特別国際理解講演会
6月6日(金)5・6時間目、2025年度特別国際理解講演会が行われました。
約30年前に内戦そして大虐殺という悲しい過去をもつルワンダで、20年以上も無償で義足を提供する活動を続けているルダシングワ真美さん、ガテラさんご夫婦にお越しいただき、ルワンダの文化や歴史、そして義足を提供する活動に懸ける想いや今後の展望を話していただきました。
【生徒の感想を一部紹介します】
● 本日お聞きした「山と山は出会わないが、人と人は出会う」ということわざが印象的でした。 たった一人との出会いも人生・世界を変えられるのだということを この講演会を通して学ぶことができました。最初にハードルの高い試練 がくることで「次は何でもできる!」と思えたという言葉を聞き、真美さんとガテラさんの意志の強さに尊敬の念を覚えました。
● 講演会でお話しくださった内容は、美談でもなく、思い出すことすら苦しいようなことだと思う のですが、ありのままをお話しくださったことに大変感謝します。争いというのは縁遠いことではなく、実際に身近に起こってしまうことだという恐ろしさを感じました。
● 私は日本で生活をした経験しかないので、民族という感覚があまりありません。私にとって「民族」 は個性を表せるもの。という考えでしたが、「民族」ということを全く意識せず、1つの国の「国民」として生活できることがどれだけ幸せで大切なことなのかを知ることができた。
● 義足の工房が政府による強制撤去の対象なってしまっても、義足づくりを続ける決断をされたことに驚き ました。必要とする人がいれば、困難な状況にあっても信念を持ち続けて 活動をし続けていることが素晴らしいと思いました。作るだけではなく、義足づくりを多くの人が学べるようにしたり、知識や技術が身に ついた人々が職につけるような取り組みをしたり、「人のため」に行動、活動をされていることに感銘を受けました。
2025/6/5 国際科2年生対象 豪州講義
今年8月、国際科の2年生は、国際科のカリキュラムの中でも大きな柱となっている「オーストラリア海外研修」を予定しています。研修前の事前学習として、オーストラリア研究の第一人者である関根政美先生(慶應義塾大学名誉教授)を講師にお招きし、2年生にとっては2回目となる「豪州講義」を実施しました。オーストラリアの歴史、日豪間の歴史的関係、オーストラリアの豊かな資源と諸外国(英国、中国、日本、その他の諸外国)との貿易関係、オーストラリア大陸の地理的な特徴、オーストラリアの人口割合の変遷(移民、難民の受け入れ)、現在の多文化社会の状況、白豪主義から多文化主義への移行とその目的など、多様な面から内容の濃い講義をしていただきました。まさに、本格的な大学の講義を受けているような貴重な時間となりました。

2025/4/17-19 国内語学研修 Language Village in Shizuoka
2025年度国際科入学生が、2泊3日で静岡県にあるLanguage Villageへ国内語学研修に行ってきました。入学後すぐの宿泊行事で緊張している生徒もいましたが、研修施設内は『ALL English』での環境でも高い志を持ち、みんなで研修を充実することができました。
参加した生徒たちの感想を一部掲載させていただきます。
・英語の勉強に対する気持ちが高くなり、さらに上を目指したいと思った。
・確実に前より、海外の方の英語を聞き取れるようになったと感じる。また、話すことにも抵抗が大分無くなった。もっと英語で話せるようになりたいと思っているので、来年の海外研修では、流暢に話せるようにして、ホームステイ先の方とたくさん会話をしたい。
・英語を話すことにためらいがなくなった。そして今より英語や外国語を話せるようになりたいと強く思う。
・臆することなく英語を話せるようになった。そして、表現のバリエーションが豊かになった。

2025/4/14 国際科Speech Contest & Welcome Program 2025
去る4月14日(月) 第24回 橘高校国際科英語弁論大会並びに国際科新入生を歓迎するウェルカムプログラムが開催されました。
第1部の弁論大会においては、昨年度の国際科1、2年生全員が4か月以上をかけて準備し、授業内グループ選考、クラス選考を経て、それぞれ4人、計8名が本選に出場しました。
幸せとは何か、認知症とどう向き合うか、批判的思考力と表現、教育の大切さ、歩くことの恩恵、自動翻訳に頼らない意義(奨励賞)、失敗を恐れない(優秀賞)、エッグセオリー(最優秀賞)、などそれぞれが自分の思いを熱く英語で語りかけました。優秀賞、最優秀賞を獲得した新3年生の2人は県の英語弁論大会への出場権を獲得しました。今後の更なる健闘を期待しています。
第2部の国際科ウェルカムプログラムにおいては、昨年度学校外で活動したことについて発表し、称えあいました。スタンフォード e-Kawasakiプログラム、文科省日韓高校生交流、米メリーランド派遣プログラム、川崎・富川高校生フォーラム「ハナ」、その他多くの活動の紹介があり、国際科の生徒の学びの広さと深さを改めて実感することができました。














