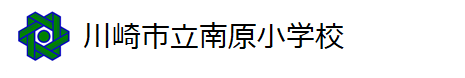校長あいさつ(2月)
凛とした寒さの中にも、春を感じるような光が差し込む2月です。
2月になります。
2月3日が節分、そして4日は立春。暦の上では新しい春を迎えます。
今月、学年ごとに予定している今年度最後の授業参観(学習発表参観)は、「これまでの学習成果を総合的に生かし、発表する活動を通して、自分の成長を感じ、相互に認め合う態度を深められるようにする」「一つ上の学年の発表を見て、これからの見通しをもつとともに、次の学年への意欲をもてるようにする」とねらいを設定して進めています。
この取組は、キャリア教育の一環として大切に位置づけているものです。
そこで今年度も保護者の皆様にご覧いただく前に、一学年下の子どもたちにリハーサルを見てもらう機会を設定しています。
こうした活動を通して子どもたちが今年度を締めくくり、次の学年への憧れの想いをもって、新しい春を迎えられるようにと願って計画しています。
今年度、南原小学校はキャリア在り方生き方教育研究推進校として、教育活動を進めてきました。子どもたちの想いを大切にしながら、子どもたちを育む言葉・子どもたちを育てる教師のまなざしを意識しながら、「南原ならでは」の教育活動を展開できるよう努めてきたつもりです。
学校評価アンケートの「学校が楽しい場所だと思う」「南原小学校で学ぶことで自信や誇りをもてましたか」という設問では、どちらも約95%の子どもたちが肯定的に回答しました。
しかしながら、文部科学省が示している「誰一人取り残されない教育」という言葉を字義通りに捉え、子どもたち一人一人の顔を思い浮かべると、まだまだ努力と改善の余地があると言えます。

今年度は、創立 40 周年記念事業の他に、「子どもたちが創る『自分たちの学校』」として様々な新たな取組が見られました。

それに伴い、企画運営をする高学年はもちろんのこと、全校の子どもたちの多彩な活躍の場が設定されました。

校内でも FRUIT ZIPPER の曲に合わせたダンスを幾度となく目にしました。このグループは、アイドルグループとしては、あえてセンターを固定するのではなく、「全員がセンター」「全員が主人公」「リーダーやセンターは置かずに全員一直線である」ことにこだわってプロデュースされているのだと耳にしました。
すべての“かわいい”は、同じ物差しで測れない
“かわいい”の定義はひとそれぞれですよね。自分にとっての“かわいい”が正解ですし、同じ物差しで測ることはできないと常々思っています。
(木村ミサ:総合プロデューサー)
今年度も残り2ヶ月。
一人一人がもつ唯一無二の良さや可能性を見つけ、1年間で伸ばしたその良さと可能性を大いに発現できるよう、教職員一同、力を尽くして行きたいと考えています。
今月も地域の皆様、保護者の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
登録日: / 更新日: